|
モノローグ的ドグマな読書感想 [郷土書篇] 2005年~ |
※ 15. 詩集『STORY』 郷よしゆき 水星舎 1012.2.20 14. 麗日の会 第53回 自作詩朗読の午後 2012.2.25 13. 弘前城築城四百年映画祭 HARAPPA 弘前中三8F 2011.12.10-11 二行詩集『季節』 圓子哲雄 朔社 06.11刊 2011.11.14 12. 弘前劇場「海辺の日々」 2011.10.30 スタジオ・デネガ 11. 劇団「雪国」 最終講演「煙が目にしみる」 2011.10.29 弘前文化センター 詩集『極楽とんぼのバラード』 小笠原眞 ふらんす堂 08.9刊 詩集『青くあれ』 高橋憲三 土曜美術社 11.4刊 詩集『津軽弁の詩』(藤寿々夢、水星舎) 06.10刊 詩集『48歳のソネット』 小笠原眞 ふらんす堂 05.3刊 詩集『耳を澄ます』 黄河陽子 砂子屋書房 10.9刊 詩集『ほしの樹紋』 対馬正子 書肆青樹社 10.3刊 詩集『遠い瞳』 一戸惠多 弘前詩塾叢書4 北方新社 10.4刊 詩集『雫』 吉野惠、弘前詩塾叢書3 北方新社 09.11刊 10. 詩集『甘溜り』 児島倫子 弘前詩塾叢書1 北方新社 09.7刊 9. 『道しるべ』 石黒英一 私家版 2007.10刊 8. 『あおもり文学の旅』 阿部誠也 北方新社 06.11刊 7. 詩集『時折風にゆれて』 黄河陽子 水星舎 06.7刊 6. 詩集『大銀杏の下を』 工藤浩司 北方新社 06.4刊 5. 詩集『ひとりぼっちのおとうさん』 渋谷 聡 漉林書房 05.12刊 4.『一輪咲いても花は花 葛西善蔵とおせい』 古川智映子 津軽書房 03.6刊 3. 詩集『ゆめ旅』 一戸郎 青森県文芸協会 05.8刊 2. 詩集『オパール色の交差点』 楠美明子 私家版 04.9刊 詩集『下北・未完の旅』 佐々木髙雄 企画集団プリズム 04.11刊 1.『生誕百年記年 石坂洋次郎集』 石坂洋次郎の会 非売品 2000.10刊 br> . 詩集『STORY』 郷よしゆき 水星舎 1012.2刊 12.5.13 詩誌「風」同人の郷よしゆき氏が水星舎から第三詩集『STORY』を上梓された。あとがきによると、詩人自身の「物語」であると同時に、人類の潜在意識の奥底に深く刻まれた物語であるという。 生命誕生四十億年の太古の歴史をなぞり、ウルム氷期の遠い記憶の底や白亜紀の小さな琥珀から、今日生きるために流した一筋の涙が生命の原石となって輝くのを遠く透視する。いや、もっと、ビッグバンから生命の誕生へと至る遠い物語の底で、母達の子宮とともに海へ沈む原始の太陽の記憶へと遡及しながら、輝くために生まれたこの地球から、銀河に封印された人類の物語へと帰還する。誕生と滅亡を繰り返す数多の物語がありながら、常に未決のまま物語を再出発するのである。 恐山の賽の河原で風車が回る音に耳をそばたて、三内丸山や亀ヶ岡で縄文の臭いをかぎ、竜飛岬の風を受ける。そして、岩木山の頂きに立ちブナの森を見下ろす。それらから遠い光りと闇の国を通過しながら、また物語を始める。 詩は四行詩が基底にあり、詩集も四編ずつⅣ部からなり、形式美と内容が一体となっていて、寡作だけに詩句も凝縮して審美的である。郷氏は、物語の基底に共同幻想のようなものを措定していて、どの詩にも通奏低音が奏でられている。それは、郷氏が学生時代にフッサールを研究されたこともあってか、物語の底に常に流れている現象学的な時間なのであろうか。暗黙知の深遠な持続のようにも感じられる。 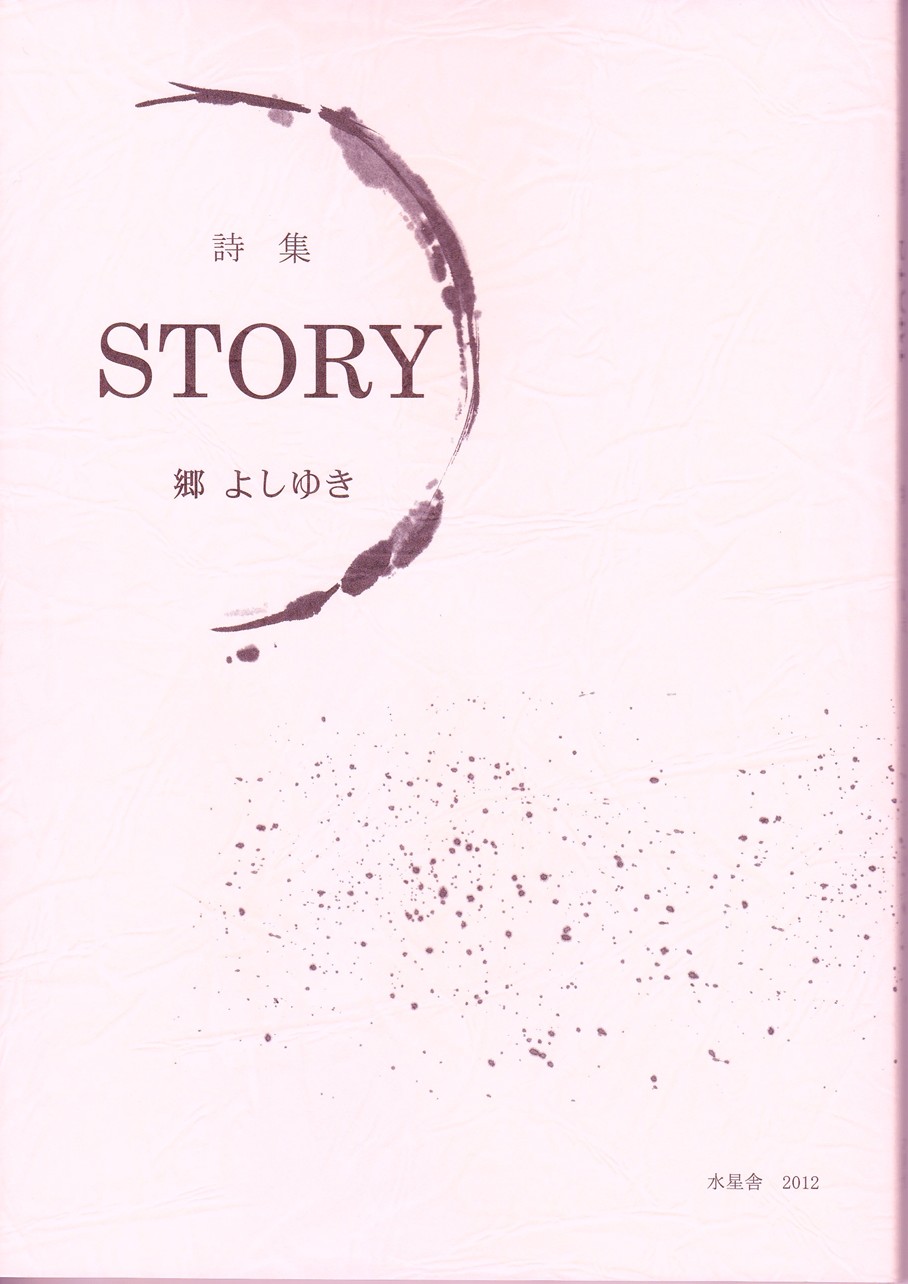 . 麗日の会 第53回 自作詩朗読の午後 2012.2.25 14:00~15:00 喫茶「煉瓦亭」 もう53回にもなるのか。数回拝聴したことがあり、今回は十年ぶりぐらい。ずっと拝聴したかった朗読会だが、遠慮してきた。いや、仕事で無理だったのだ。十年ぶりに拝見する朗読者たちの経年をまず感じたのが正直なところ。それだけ愚生も歳をとったのだ。先輩格たちのいまだ朗読のしっかりしたことに感嘆するとともに、若手の方、といっても愚生の世代、あるいはより若い人たちの、人間味が丸くなって温かくヒューマンなお人柄がにじみ出ているのにも驚いた。 最初に竹森氏にお声をかけられたのが嬉しかった。主宰者の葛西美枝子氏に詩誌「風」に一戸氏を推薦してくれた謝意を述べることができ、路上社の安田氏に遠くから声をかけられ、泉谷氏に改めて自己紹介ができた。ある朗読会でご一緒できた市田氏と田澤氏からもお声を頂いた。実に有難かった。小笠原氏の姿が見えない。おられれば、フェイスブックの友達承認を頂いた謝意を申し上げたかった。 テーブルに居合わせたのが對馬氏。二人だけだったのでよく拝顔できた。詩集を所持し読んでいるが、後書等に経歴がほとんどなく、まだ愚生のHPに記載できないでいる詩人。街の新聞にも「詩の窓」に掲載している常連でもある。どの詩誌の同人だったろうか。隣のテーブルに葛西千秋氏。時々間近に見合す距離だった。若い頃私家版の詩集二冊上梓しているようだが、見入手。彼もまだHPに掲載できない愚生にとっては未知の詩人。「漣」の同人であったり、長い間「弘前文芸」の詩の部門の編集担当をされてきた詩人である。 幾編かは既に同人誌掲載で知っている詩だが、自作朗読により、例えば船越氏の「街の灯書店万歳三唱」などはニューヨークの臨場感がある。実際訪問した時の作だという。葛西美枝子氏の「ポルトガル旅情 人と人との間で」も実際にポルトガルでの詩作であるという。羨ましい限り。 櫻井氏の年季、工藤氏の貫禄、ともにその朗読にただただ敬服。泉谷氏は以前にも何度か拝聴した感のある前台詞だが、相変わらずの言葉一つ一つに熱い情感を込めた、モノローグ的な内容、つぶやきのようだが、ずっと路上派的な雰囲気を秘めたすごさがある。街の詩界では、詩誌「朔」の小笠原眞氏の二段組み十三ページにわたる評論「泉谷明は日本を代表する路上派の詩人なのだ」が話題になっているようだ。 それにしても皆さん、流石朗読が上手い。特に澄んだお声で歌うような對馬氏、熟練を感じさせる船越氏、生まれつきだろう竹森氏、脱帽。 朗読終了後、司会役でもある葛西氏よりご指名で感想の発言を求められたから嬉しかった。そのこともあって、思い切って船越氏に自己紹介できた。 ある朝 目覚めると 世界が背を向けて立っていることがある 世界を覗く窓のような液晶画面は 墨を塗ったように真っ黒のままであり 玄関に届けられた新聞は めくってもめくっても真っ白なままである ワタシに届くニュースなど 一つもないとでもいうように 届かないニュースは どこでもある いつでもある 世界がこんなに小さくなっても 世界の構造は歪曲し 褶曲し 決してつながらない思想や欲望の断層を いくつも内側に控えているのだから ある朝 目覚めると 世界がすでに背いていることがある ・・・・・ ある朝 目覚めると 世界がやさしく迎えてくれる そんな朝は くるだろうか ・・・・・ (「そんな 朝が」工藤浩司) 愚生の詩作方法に極めて近いのに驚く。対比的で弁証法的な、かつ序破急的な三連。好きな形である。五十行近い。その長さゆえに深い思想が表現されている。哲学的な詩だ。愚生はどうも同人誌二箇所に投稿するに三十行の限界を感じながら詩作してしまうが、反省を要するところであろう。 「世界の構造は歪曲し 褶曲し/決してつながらない思想や欲望の断層を/いくつも内側に控えている」。鋼鉄な男の詩、そういうイメージも濃厚である。 ※ ・・・・・ 雪泥棒 雪泥棒 地面に落ちる前に拾って 夏の猛暑日に撒いて下さい あどけない林檎に当たらないように 静かに そっと 雪が白くなかったら 雪が赤いと血みたい 雪が緑だと草原みたい 雪が青だと空か海か分からない やっぱりお城の壁と同じ 白がいい 白い雪が全てを埋め尽くし 雪が季節のスイッチリセットして 花鳥風月 一年が始まる (「雪」對馬輝子) 傑作である。どこかに永遠にとっておきたい名作である。詩人の童謡風な朗誦がずっといつまでも頭の中に残響する。方言詩の語りもいいが、時代を超えた歌のような、朗読詩の最たるものであろう。 「雪よ/悲しみに打ちひしがれた/心だけは押し潰さないで」 ※ ごはんつぶひとつ 膝にこぼれているのをみつけました ・・・・・ (「なんともさびしく」泉谷明) 泉谷大先生からみて、愚生は還暦を迎えたばかりだが、同様に、なんとなくさびしくなります。 ※ それでも 恋慕に似た不安が交錯する 初恋の人と再会するようで胸が震える 私たちはたがいの鼓動を指先でたしかめあった 類型的な地名、日時、人名の疾走。でも、暖かく緩やかなビート。温情あふれるストリート・ポエム。上の三行は異質だが、この女流詩人の初期のもう一つの感性を髣髴とさせてくれる。 サンフランシスコの路面電車や中華街に触れながら、その日常生活まで下りた現実描写は流石なものである。どうやら、ビート詩人の多くがそうであったように、女流詩人もまた禅や老荘にますます強い関心を向けているようである。老荘や禅のファンとしては共鳴するばかり。愚生、ロックは聴かないが、一応長らくのジャズファンのつもり。因みに、「すが」に入りびたりであった学生時代前半、すれ違いで先にそこに来ていた人たちが、先輩格の工藤浩司氏や泉谷明氏たちだった。それにしても意外だった。何ともヒューマンになっておられることか。 「私たちの魂にも どうぞ 灯りがともりますように」 ※ 貧困者の発生は国の無策の顕現なのに 人から集めた金で 自分たちが暖衣飽食して それでお仕舞い (「2012年日本」竹森絵美) その他のみんなは「ぺらぺらになるまで/自分をすり減らして」いるというのに。ところで、マヤ暦におけるチラムバラムの予言って知らなかった。現在の時間軸が終わるという。 ※ 夜更けの灯りは凍ちつき シャッターを降ろした花屋の前で立ち止まる 捨てられた一鉢のシクラメンが 凍て蝶のように花びらをたたんでいる ・・・・・ 忘れてはならぬ記憶と 忘れねばならぬ記憶を 一絡げにして深々と雪に埋める そして すべてを喪った者の潔さで 未知の領土に頭を垂れて 異教の世界へ下りていく (「夜更けのソネット」櫻井麻古人) 第一連が何とも、枯淡の境地。ソネットだが、憧憬する内容の詩境。第三連の強い意志の諦観と終連の悟りとしての諦観。すべてを喪った者の潔さ、それは全くの清さでもあろう。頬に感じるきりっとした冷たさのような、透き通った世界。存在者が存在に帰る回帰。 ※ ああ、ポルトガルのお月さま 丘に上のお城を頂点とする静かな町 教会の石畳の坂道を 手を取り合って行く姿が見える 朝のお祈りの時なのかもしれない ポルトガルの空よ 空はどこまでも続いている 人と人とをつないでいる 登場人物に無知な上に、まずパルメラ市が分からなかった。以上の詩句には深く感じるものがあったが、帰ってからネットで調べた。 WACというのは World Art and Culture Exchange 「世界芸術文化交流会」ということだった。WACが主宰する「グランデ・レゼルバ 日葡芸術の紫玉名品展」。同会のHPによると、赤尾氏とは、同会の最高顧問(ジュネーブ、ウィーン国際機関代表部大使歴任後、元在タイ日本大使、前国際機関ASEANセンター事務総長)であった。同会は、芸術とワインの出会いを記念して芸術ワイン騎士団を設置しており、その芸術ワイン騎士任命に日本美術家を代表して詩人・葛西美枝子氏が授与されたのだ。授与後、葛西氏の詩の朗読が行われたという。「葛西氏独特の暖かみのある朗読の調子で日ポ両国の親好と平和への願いが込められ日本人からポルトガル人への心のメーッセージが届けられた」と。拍手喝采。さらに、葛西氏により古城の中庭において子供アートセッションが行われたという。素晴らしい。墨筆により一層詩情を高めた作品が評価されたのだ。子供たちが「言葉の壁を越えて葛西氏の指導に対し素直に向き合う平和な空間が生まれていた」という。ブラボー。 ※ あなたは知らない あなたがこの家に来るよりずっと前から わたしがここに居たことを ・・・・・ あなたは知らない ため息を吸い込むごとに わたしが 深い色になっていくことを (「誰が決めたわけでもない」市田由紀子) 静かに音楽が流れている。人には聴こえない室内楽が。足音はそおっと。黙したデュエット。 ※ あなたもまた自分の影を引き連れ 野の道を漂いながら ひとすじの残照 蜃気楼の向こうに見えていたものが いつの間にか 手の触れる位置にあり 光溢れる道標の前に立ち尽くしている ・・・・・ ぼくたち 生まれた場所を あまりに離れ過ぎたため 去ってしまったものが いっそう遠ざかってしまった ・・・・・ 遠い場所にたどり着くため 一歩が ぼくたちには必要なのだ 暗い歴史には 強靭な出発がつきまとう それらにも 幽かなひかりが並び始め たどり着くはずの場所には そこにふさわしい朝がやってくる (「野の道を漂いながら」葛西千秋) 抒情詩だ。青春の感性をいつまでも保持できる才覚が冴える。青年は誰しもこのような詩に憧憬し、自ら書きたかっただろう。そして、その気持ちは老いてもなお誰しもが持ち続けているように思われる。それを見事に果たし、表現しているのだ。自分の影、野の道、残照、蜃気楼、道標という選び抜かれた言葉が抒情を誘う。詩を書くものが時々立ち戻って来る、そして、恐らくは晩年により深めることになるだろう世界。 回帰する所。それは故郷であり、詩を感じ始めたこころの故郷であり、どれほどそこから離れようと、流離おうと、帰還すべき純粋さ。いま、そこがあまりにも遠すぎようと、決意が必要なのだ。いまだけではない。いつでも。 シューベルトのピアノ曲や歌曲を聴きたくなってくる。 ※ 上見れば 虫っこ 下見れば 綿っこ 午後の空を灰色にぼかし ・・・・・ 積もった面はふわふわの綿 大粒の牡丹雪がとめどもなく ・・・・・ 如月の公園は雪に埋もれ 薄墨桜番は堅い 風が吹く 雪が走る 走るとは傾くこと 雪の中を わたしは かい潜るように急ぐ (「二月というのに」田澤ちよこ) 簡潔な詩句に津軽の季節が深く込められている。でも、言葉は雪のようにさらっと、純白に。ポエムが降り注ぐ。 もう一つ長めの詩「藁」を朗読された。ひとが縄で庭木を放射状に囲う。結び目のように藁とひとが一緒に冬を過ごし、眠り、春の風に目ざめそれぞれの道をゆく。縄は一瞬に解けて藁にもどり、遠く彼方の空へ。終連が実に素晴らしい。 皆さん、本当に上手いんですね。感服するばかり。 [※ 葛西美枝子氏と葛西千秋氏の「葛」は、人ではなくヒ] 朗読会のあと、これらの詩を印刷した芳賀さんの事務所に寄る。郷よしゆき氏の第三詩集がほぼ出来上がっていた。楽しみである。田澤ちよこ氏が最近詩集を上梓されたことを知る。街から久々に詩集の刊行が続く。嬉しい限り。目立たなくとも、確かにこの街は、「音楽の街」同様、「詩人の街」なのだ。 . 弘前城築城四百年映画祭 HARAPPA 弘前中三8F 2011.12.10-11 昨夜は映画『夢の祭り』のセレモニーと上映があり、行きたかったが九時近くまで職場にいた。原作・監督の長部日出雄の講演があったのだが、実に残念だった。あとでT先生から伺ったが、120人定員に対し160人くらいの観衆だったようである。120人というのは予めの限定者たちらしく、その中には街のペンクラブ会員も含まれているようである。愚生も事前に招待文を頂いていたような、単なるお知らせであったような、よく分からなかった。 二日目の午後、三本中の一本を観た。石坂洋次郎原作の『石中先生行状記』。1950年、東宝、96分、35mm。監督は成瀬辰喜男という人。白黒である。最初、台詞が早すぎて聴き取れなかった。でも聴衆はくすくす笑っている。愚生は何を話したのか聴き取れなことが度々あった。次第に慣れていった。そもそも、映画を見るのは何十年振りだろう。 三話構成のオムニバス映画。いずれもロケが弘前周辺となっている。岩木山が大きく映し出されての田園風景。稲穂溢れる農道を藁積み馬車が行く。昔の岩木橋が懐かしい。農家の囲炉裏のある屋敷が懐かしい。夜の暗さが本物である。「隠退蔵物資の巻」「仲たがいの巻」「干草ぐるまの巻」。あとでパンフを見てびっくり。いまだ芸能人どころか俳優にも全く無知だが、主役が池部良や三船敏郎だった。小さなエピソードの中に、街や農家の人たちの愛情豊かな熱いものを覚える。口数少なくとも、情愛と他人への思いやりが篤かったのだ。予想外に、開始前に長部氏のお話があり、楽しく意義深いものがあった。 二日目。まず午前の『夢の祭り』を鑑賞。長部氏の説明が嬉しくとても有難かった。愚生、長部氏を仰げたのは今回で二度目に過ぎない。しかも、一回目が何の時であったかも思い出せない。何とも情けない。それだけに実に嬉しかった。ずっと、我々の憧れの人物である。 津軽三味線の競争心から、流しの旅をし、隠棲しての集中的な修行、芸そのものへの質への執念。コルトレーンを思い出す。牧良介の素晴らしい演技による盲目の乞食請い、三味線を放棄し隠遁した名人、そう、老荘、禅の世界である。岩木山、そして久遠寺山の背景も素晴らしかった。ブナの森の緑も、雪景色も、全体的に美しい画面だった。本当に、純文学であり、珠玉の芸術作品だった。それでいて、心を掴んで最後まで離さない。最後は、特に、数十秒の長編文学だった。 午後、クラシック・ファンは『オーケストラ!』を鑑賞。字幕が見えないのを覚悟で座ったら、ちゃんと見えので助かった。何も言うことがない。ユーモアを少し含めた、感動映画。膨大なクラシック界では、著名な音楽家によくありうる話である。とにかく、感動、なにせ、バックがモーツアルトのピアノ・コンツェルトから始まって、チャイコのヴァイオリン協奏曲。もう、それだけで感動してしまう。街角や夜のプレイヤーで糊口を凌いでいる者もあるが、演奏家からとうに離れていた者による臨時の偽装オーケストラ。リハーサルなしでの演奏中での調性の整えと調和、合奏の達成と、指揮者とソリスト、皆との合致、神がかりな、いや情愛による成就の痛快感。 どの作品にも心ざわざわとし、涙ぼろっぼろっ。黙読、黙視、目をつぶって聴く沈黙に住む輩には、映画はやはり刺激があまりにも強過ぎた。 主宰者のNPO法人HARAPPAには脱帽の限り。三上氏、品川氏、関与している皆さんに敬服の限り。品川氏って、愚生、大学1年の時に映画研究会に所属していたが、その頃から話題の人であり、詩人の藤田晴央氏らと同人誌も作っていたようなような。記憶が薄れてしまった。教員をされたのかな、世永先輩や山谷さん、北海道のハンサム先輩さんたち、どうしておられうのだろう。『日本春歌考』上映、大島渚論、自作シナリオなど思い出す。受験浪人から大学二年まで、俳優はつゆ知らず、監督を選んで結構映画を見ていた。そして『ソドムの市』と『愛のコリーダ』のショックが大き過ぎて映画鑑賞を止めてしまった。パゾリーニは詩人として再び興味を持っていったが。懐かしい。それだけに、映画鑑賞の少なかった人生が、いまとても悔しい思いでもある。哲学、文学、絵画、音楽の好きな人間にとって、映画とは、総合芸術であったはずなのに。 (2011.12.11) . 弘前劇場「海辺の日々」 2011.10.30 スタジオ・デネガ 海岸沿いの町の日常的な情景。変哲のない日々を、具体的で詳細に展開している。作者の現実世界の凝視、観察力に感服させられると同時に、例の如く会話の中に哲学的な意味深長な言葉が挿入される。 地方新聞社の支局の通信局員とその妻と娘、その妻の兄である前町長、役場の総務部長、教育委員、民宿兼大衆食堂の店主、バスの運転手や学生等々、様々な人々がそれぞれの世界を持ちながらも一つの場で生きていることを交歓しあう人間模様。もうそこだけで一つの街であり、小国家のような、多重でしかし心の芯で統一されたような世界の描写のように感じられた。前にも観たような気もするが、素晴らしい作品だと思った。 役者も、当劇団の重鎮の他、いつものように他の街の演劇研究会の主役、県都のある劇団の主役が活躍し、舞台を生き生きとさせてくれる。それにしても、皆さん、台詞をよく暗記し、身振りと同時に間合い良く発するものである。役者にもただただ感服するのみ。 文化庁芸術祭参加公演もさりながら、文化庁芸術振興費補助金の「トップレベルの舞台芸術創造事業の一環であるから流石である。県立美術館でも大活躍の長谷川氏は県を代表する演劇人であり、弘前劇場の稽古場も県都であり、もう劇場の名称が変更されるのではと危惧の念を抱きながらも、まだ街のスタジオで公演してくれておるから、とても有難い。 わが街の文化活動も衰弱の一途を辿っているように思われる。伝統文化を除くと、演劇を始め、文学や絵画の世界では他市にかなり後れをとり、ますます引き離されている感じである。活発かと思われてきた音楽と詩の分野も、他市の上昇率に比べれば沈滞気味なような気もする。大きなコンサートや詩の開催もすべて県都である。別に他市は他市、気にすることもなく他市の独特な世界を教わり味わうのが何よりの楽しみだと思うのだが、意図せぬ他市との関係での内部的な消滅を恐れているのである。より認識を深めより良い志向を持つには差異化は必要なのだ。決して垂直的にではない水平的な差異化が。垂直はあくまでも個の世界だけで。街および周辺の人口減少も影響しているかもしれない。もともとない経済力がますますか細くなっていく。若手がいなくなる。残された若者たちも活力が出てこない。どうにか良き方法がないものかと按じても、自分自信も同様、経済力もなく身動きでず何もできない不様である。それだけに、弘前劇場や内山善雄トリオ、街のチェロイスト、最近は『風』の同人の彼などに、何とか頑張らなくてはと一方的に鼓舞されつつあるのも正直なところ。でも、何にも能力なく、身動きができないか。 出演:高橋淳、青木峻、福士賢治、長谷川等、林久志、田邉克彦、永井浩仁、黒滝奎吾、柴山大樹、小笠原真理子、国柄絵理子、寺澤京香 作・演出:長谷川孝治 スタッフ:野村眞仁、中村昭一郎、田中守理、鈴木徳人 弘前劇場は早くから歴としたHPを持っており、そこから活動状況や情報を得られるから有り難い。それにしても、HPもまた素晴らしい。 . 劇団「雪国」 最終講演「煙が目にしみる」 2011.10.29 弘前文化センター 門外漢で相変わらず演劇音痴だが、観劇に行く前から心でもう泣いている。もっと続けて欲しい。「雪国」が消えれば、街の演劇界も半減してしまう。いや、一般の市民にとって、もう街には劇団がないも同然かもしれない。それだけに、これまであんまり観劇できなかったのが悔やまれる。十八番のような久藤達郎の「東風の歌」と「林檎事始」、阿部公房の「どれい狩り」など、木下順二の「三年寝太郎」など、チェーホフの「白鳥の歌」など、他に田中千禾夫、オニール、そして「西の人気者」や「鬼の詩」。他はあまり記憶がないが、情けないほど訪れた回数が少ない。いずれも、誰の心をも打つだろう、人間味のある、ヒューマニズムの演劇だった。 原作者の堤泰之について無知だが、場はこの街の斎場のようである。弘前劇場のある作品を思い出す。家族、ひとりひとりの人生が描かれており、とてもヒューマンである。時に幕間的にユーモアを交えながらも、数回涙がどっと零れそうになった。ユーモアと悲しみを交え、その上で生きることを顧みさせ、生きていく喜びを感じさせてくれる、そんな演劇の良さを持った作品のように思われた。また、文学的に、焼き場に送られる死者の登場が、なお生と存在の消滅について深く感じさせるものがあった。劇的なクライマックスはないが、インドネシアから行方不明の長男から「蝶の谷」の手紙が届いた感動と、葬儀に尽力する知名人に親族が嫉妬し誹謗する場面への同じ人間としての不安をすこぶる覚えた。 木村氏が亡くなられても、立派に公演されているだけに、とても勿体なく思った。63回もの公演。本当にお疲れさまでした。誰もが敬意を表しておるこであろう。前列の真ん中に、白髪となったSがいる。大の演劇好きで、長らく街の演劇協会の会長をやっていたようだが、どんな気持ちなのだろう。彼は「雪国」を最も愛していたように思う。 実に淋しい思いである。ある意味では最も大切なことと思う「弘演」は社会派過ぎるような、愚生には意味的に最も興味のある「弘前劇場」は日常生活を据えながら時に会話に観念的過ぎる所があるような、また事務局が県都に当たるため、とにかく一般市民は遠慮がちになる面があるように思う。サザンカンフォートや、まだ一度も拝見したことがないかもしれないプランクスターは、客席に就くには歳が恥ずかしくなるような。前者は笑いのシリーズの時もあり家族で観劇したこともあるが、一人では行き辛くも思う。学生のマップレスを含めたとして、他市ではますます演劇が盛んになっているだけに、「雪国」が無くなると、寂しさが増してくる。夜行館が去った時、畑澤氏が去った時、そして弘前劇場が他市になった時以上に。 最初に文学に興味を持った時、文学の中には当然戯曲もあった。短歌や俳句も当然あった。それらから次第に離れていっても、敬意はずっと持ち続けてきた。いまだ詩の一編も暗誦できないでいる輩は、長いセリフを情熱的にしかも流暢に心を込めて言うのが驚異だった。身体と一体になった演劇こそ、人類最高の精神文化だ、とも時々思っている。それだけに、街の演劇界が薄まっていくのがとても辛い。最終講演をされた方々の、再出発を心から願っている。本当に勿体ない。そんな演劇だった。 キャスト:木村健悦、五十嵐トキ子、工藤陽子、松山貴美子、石戸谷眞一、鎌田利雄、小山内敬子、盛岡節子 演出:工藤文弘、その他に音響効果:日景正彦、装置:小野俊郎 以下に、パンフにある公演記録の一部を記述し、その偉業を少しでも感じたい。 S26 第 1回公演試演会 記念祭(チェーホフ)、葉桜(岸田国士)、長女(阿木翁助) S28 第 2回公演会 みごとな女(森本薫)、死の前に(ストリンドベリ) S28 第 3回公演会 アスパラガス(秋田雨雀)、薔薇の一族(小山祐士) S29 第 4回公演会 藤原閣下の燕尾服(飯沢匡)、にんじん(ルナール) S29 第 5回公演会 チェーホフの夕べ(「熊」「結婚申込」「路上」) S29 第 6回公演会 5周年記念 検察官(ゴーゴリ) S30 第 7回公演会 ワーニャ伯父さん(チェーホフ) S30 第 8回公演会 東風の歌(工藤達郎) S31 第 9回公演会 にしん場(中江良夫) S31 第10回公演会 閣下(北条秀明) S32 第11回公演会 たらちね海(工藤達郎) S32 第12回公演会 白鳥の歌(チェーホフ)、ケルナー先生の胸像(押川昌一) S33 第13回公演会 クノック(ジュール・ロマン) S35 第14回公演会 十周年記念公演 宮澤賢治伝(工藤達郎) S36 第15回公演会 終末のない話(チェーホフ) S37 弘前芸協例会共同公演 漁船天祐丸(ハイエルマンス) S37 第16回公演会 東風の歌(工藤達郎) S38 秋田雨雀の夕べ 水車小屋(秋田雨雀) S38 第17回公演会 白夜(寺山修司) S39 第18回公演会 検察官(ゴーゴリ) S40 第19回公演会 海の星(八木隆一郎) S41 成人式公演 野の声(八木隆一郎) S41 第20回公演会 明治の学校(工藤達郎) S42 成人式公演 月冴ゆ(二宮千尋) S43 成人式公演 獅子(三好十朗) S43 秋田雨雀の夕べ 白い晴着(ポール・グリーン) S44 成人式公演 湖の娘(八木隆一郎) S44 第21回公演会 林檎事始(工藤達郎) S45 成人式公演 こねずみ(堀田清美) S45 第22回公演会 神通川(本田秀雄) S46 成人式公演 百姓の嫁っこ(後藤志げお) S46 第23回公演会 煙突のあるオアシス(大橋喜一)、百姓の嫁っこ(後藤志げお) S47 成人式公演 煙突のあるオアシス(大橋喜一) S47 第24回公演会 東風の歌(工藤達郎) S48 第25回公演会 書けない黒板(こばやしひろし) S49 第26回公演会 創立二十五周年記念 島(堀田清美) S50 第27回公演会 破戒(島崎藤村) S51 第28回公演会 波止場乞食と六人の息子たち(八木柊一郎) S52 労演公演 民話劇の夕べ 二十二の夜待ち(木下順二)、彦市ばなし(木下順二) S52 第29回公演会 ぼっちゃん(夏目漱石) S53 第30回公演会 地平の彼方(オニール) S54 第31回公演会 創立三十周年記念 鈍琢亭の最期(田中千禾夫) S55 第32回公演会 東風の歌(工藤達郎) S56 第33回公演会 幽霊はここにいる(安部公房) S57 第1回春の公演 小さな広場(ゴルドーニ)、白鳥の歌(チェーホフ) S57 第34回公演会 西の人気者(ジョン・シング) S57 第2回春の公演 鬼の詩(藤本義一) S58 第35回公演会 千鳥(田中千禾夫) S59 第36回公演会 夜の季節(マイケル・V・ガッツオ) S59 第37回公演会 夕餉すみ候や(田中千禾夫) S60 第38回公演会 創立三十五周年記念 どれい狩り(安部公房) S61 第39回公演会 ばさら(田中千禾夫) S62 第40回公演会 ハーベイ(マリー・チェイズ) S63 第41回公演会 友達(安部公房) H 1 第42回公演会 マンクスウェル山荘(A・クリスティー) H 2 第43回公演会 創立四十周年記念 林檎事始(工藤達郎) H 3 第44回公演会 誘拐(八代静一) H 4 第45回公演会 無罪と無実の間(ジェフリー・アーチャー) H 5 第46回公演会 東風の歌(工藤達郎) H 6 第47回公演会 三年寝太郎(木下順二) H 7 第48回公演会 象の涙(斎藤瑞穂) H 8 第49回公演会 患者(A・クリスティー) H 9 第50回公演会 奇蹟の人(ウィリアム・ギブスン) H10 第51回公演会 ゴジラ(大橋泰彦) H11 第52回公演会 林檎事始(工藤達郎) H11 劇団「雪国」小公演 お引っ越し(畠田恭子) H12 第53回公演会 創立五十周年記念 隠人(おに)(ゆい きょうじ) H13 第54回公演会 夫のかわりはおりません(江村利雄) H14 第55回公演会 見果てぬ夢(鈴置洋孝) H15 第56回公演会 藤原課長の秘密基地(土屋理敬) H16 第57回公演会 釈迦内棺唄(水上勉) H17 第58回公演会 親すて(田中千禾夫)、夕鶴(木下順二) H18 第59回公演会 十三の砂山(寺山修司) H19 第60回公演会 耳なし芳一(小泉八雲) H20 第61回公演会 楢山節考(深沢七郎) H21 第62回公演会 春の枯葉(太宰治) 詩集『極楽とんぼのバラード』 小笠原眞 ふらんす堂 08.9刊 2011.8.3 詩集『青くあれ』 高橋憲三 土曜美術社 11.4刊 2011.8.3 詩集『津軽弁の詩』(藤寿々夢、水星舎) 06.10刊 2010.12.31 詩集『48歳のソネット』 小笠原眞 ふらんす堂 05.3刊 2010.11.25 詩集『耳を澄ます』 黄河陽子 砂子屋書房 10.9刊 2010.9.16 詩集『ほしの樹紋』 対馬正子 書肆青樹社 10.3刊 2010.9.1 詩集『遠い瞳』 一戸惠多 弘前詩塾叢書4 北方新社 10.4刊 2010.5.5 詩集『雫』 吉野惠、弘前詩塾叢書3 北方新社 09.11刊 2009.12.30 . 児島倫子詩集『甘溜り』 弘前詩塾叢書1 北方新社 09.7.30 弘前詩塾の機関紙や陸奥新報で作品を目にする詩人の、ついに上梓である。待ってました、との思いである。 旧姓では、喫茶店での若きチェロ独奏者の母親そして自然観察会でのサングラス姿の方として眺めたような、また風のうわさを耳にする方だが、でも愚生には未知な方であり、勝手な断片を誤って繋げているかもしれない。 詩集の標題作のあと『緑の円卓』を読んで、まずはもう詩の上手さに感銘してしまう。夕方に決まって広い空があるだけの理由で足が向かう空地。 思う存分ひと日を吐き出し 深呼吸できる空地 ・・・・・ 黒土が香る 忘れられた雑草が 其処だけに吹く風にそよぐ 〈さあ、ささやかなる夕餉・・・・・〉 呟きに月はするりと夜幕を伝って 降りてくる シルエットと化したヒマラヤ杉が じわじわにじる寄る シルエット化した杉、誰しもが表現したい情景であろうが、なかなか表現しきれない。本詩はそれを見事に表現したといえよう。何とも詩的であり、心理を仮託しているのは詩である以上当然であるが、短文にも拘わらず純粋な描写としても実に優れている。そして、そのような詩境からくる感慨は次の『薫風』で完全に参ってしまう。とにかく上手い。わずか三篇を読んで、その完璧さにも驚かされる。詩句だけで凝縮された、かつ密度のある作品群。もう群なのだ。 空に放たれた鯉は 光る尾ひれで 五月の風をあちこちに届ける 矢車がカシャカシャ回り 吹き流しは遊んでいるかのように空を掃く 鯉はしっかり見開いて 届けた風の行方を追っている 遠くの小枝が微かに動いた 受け取ったのだろうか ・・・・・ 風がびゅんびゅん唸る 鯉が大きく強く尾を振る 風を受けて ああ 遠い日の窓が開く また、この詩集の趣旨の一つとして神秘主義を挙げても過言ではないだろう。それは懐古の念を伴った潤いのある神秘性であり、短い詩句ながら散文詩的な光芒を放っている。詩人の目によって選ばれた目前の現実的な事象を直視しながら、その事象の奥に時間を幾重にも遡及していく深みもあり、そこからまた空間へとイメージが膨らんでいく自由さがある。軽やかな選れた感性により、意外な事象が連結され融合する。そして、それらに通底する内省的場が感じられる。特に『蔦沼浄夜』や『感傷船』に顕著に顕れている。特に後者など、大変な傑作なのではないだろうか。 詩人のそんな感性とは、例えば、 私は白のむこうに控える冬の形と大きさを ひそかに遠く推し量る 近づく心音をたよりに 冬の心臓を探す そうのようなことができる繊細で鋭利な感覚の持ち主であるそれである。寂しさと淋しさ、そしてそのどちらでもない<さぼしみ>を差異化できる特殊な知覚を持つ詩人ともいえよう。錆びていく時の傍らで生成される時を峻別でき、かつ両者の根本的な同一性をも了解可能な論理的感性とでもいえよう能力が備わっているのだ。それは天性的なものかもしれない。 最後に、内なる一点からの想像力の壮大さにも打たれた。『水の樹』と『沈黙の柱』である。不思議なな世界を紡ぐ。もう、常人を超越した才能といえよう。どこからこんな閃きが生まれてくるのだろうか。しかも、詩情を決して離れず、むしろ高踏的に昇華しているようにも感じられた。 あの日から水の樹 ・・・・・ 更に泣き続けて なのに一滴も流れ出なかった涙が 今 こんなに太い水の樹 ・・・・・ 森まで……百年 その途中で私は消え 同時に あの日から巣くった悲しみも 跡形なく消え去るだろう そうして 樹の根の跡にできる水たまりは 浄らかに いつまでも空を映すだろう (「水の樹」) 闇に沈黙の柱が立っている 水晶でできた先の尖った柱が 何本も何本も立っている 静けさが水の滴る音に破られる ・・・・・ ここは何処だろう ──夜がひび割れた谷底 沈黙の柱とは ──思いの残痕 ・・・・・ あ、何かが降ってくる 雪のような──灰? 灰は 幾日も降り続く 沈黙の柱を埋め尽くすまで (「沈黙の柱」) 詩集を上梓しながらも、まだまだ心底にたくさんの詩想や想いが潜んでいるに相違ない。 日本の近現代詩を深く探究しておられる弘前詩塾主宰者の藤田晴央氏。流石。好きで詩想を伝播し、その中から必ずや逸材が誕生することと期待していたが、然り。してやったり。その詩塾には、少なくとももう一人気になる男性詩人がおられる。ますます楽しみであり、頼もしい限りである。拍手喝采。愚生も頑張らなくては。強く鼓舞された想いである。 . 『道しるべ』 石黒英一 私家版 2007.10刊 2008.1.3 石黒氏は、簡潔な表現で、晦渋を秘めながら新たな時空をふあっと創造する地域では類稀な存在。装飾性は微塵もなく、余計な言葉は露もなく、言葉ひとつひとつがその意義さえも否定し恰も存在だけを開示しているように思わせる。だからことばとことばがぶつかり合い、一瞬、燐光が放たれ、その見えぬ残影がしばらく強く脳裏を占有する。いわゆる、一つの、詩的世界らしい詩世界であり、ほんものの詩である。 そんな内容的にはやや晦渋な、抽象的とも思われる詩世界が、幾らか分かりやすい具体性を帯びてくると尚更に心深く突き刺してくるものがある。が、それは叙情ではなく、もっと乾いた存在そのものの根源と、非在である時空間との関係の、不可避な哀しみ、とでもいえようか。次の『膝』は、その典型かもしれない。 膝 -佐藤麻古杜に送る- たわわに みのった 雪が おまえを、さそったのか いや 雪原に点滅していた 生を、拾いそこねたのか はじかれた 声の在り処を 指でたどれば 奇妙な盃に ぽろりと落ちる うろこがある 死は なだれを打ってくるというのか 膝にしたたる 無償のはいざいに 馬鹿みたいに かわいた 風声だけが ・・・・・ とにかく上手い。脱帽である。ただ、無償の「はいざい」が分からない。ある意味で「無償の」あとにどんな言葉がこようと変わりがないようにも思われるが、頗る気にはなる。仕方なく、「敗残」とか「廃残」を代置してしまう。「雪原に点滅していた生」や「はじかれた声」、一見ありふれたような表現とも思えるものの、氏の場合それらだけでひとつの独特の時空間を放っているのだ。氏らしい表現であり、それだけで詩を構築してきた自恃、あるいは潔癖さに強く打たれる。詩人としての、詩の在りかの呈示でもあろう。 この詩集は、「膝」の他に「背中」「首」「足」「爪」「髪」「みみたぶ」「眼」「膀胱」、そして「痰」「なみだ」「新陳代謝」と体に関する表題が多い特徴がある。老詩人によく見られる現象だが、氏の場合は女々しさがなく男性的な骨太さを感じさせてくれる。一方、老詩人の詩には人生の悟りゆえの自嘲や諧謔性も頻繁に見られるが、氏の場合は、自身の肉体さえ遠くに置いての、広やかなゆとり、間の空間が存在する。だから、安心でき、つねに新たな形而上学が誕生する、常に若々しささえ覚えてしまう。読む側に、新鮮な世界を開示し続けてくれている。寡作だが、それだけに真摯に、たとえややユーモラスであっても結晶化を決して忘れない、そんな持続性。 私は、ただの詩を書きつづける ・・・・・ そら! どこかで かさこそと 生きたぶんだけ からっぽの 音をたてているえはないか (『伏流』) そんな姿勢は、『アルペジオーネ・ソナタ』 で唯一率直に歌われていよう。愚生には未知な矢島三雄氏への追悼詩だが、そのまま作者自身の信念を重ねている。 ことばを おおくもたなかった おまえには 思念にあふれた たくさんの 詩があった ・・・・・ とうとうとながれる 水のおとをたしかめる みせかけではない にくせいで 眼にみえないものにも こたえていった ・・・・・ いつでも おまえの詩は 空からはみでるほどきりこんでいた ときには しぶきをあびながら 結び目をたどっていく ・・・・・ まちがっても しゃれた詩などうたうな にんげんが はじめにいったことばの おわりにこたえよ。 純粋さの一方で、戦いなのか、自問なのか、邪心さも垣間見える。心底には創作者としての悲痛なのだろうか。しかし、これもまた純粋な邪心。あたかも、『幼鳥-メシアンの光点にのりながら』の、「詩はどこにもない/詩はどこにでもあると/波状しながら問いつづける」かのように。詩に憑かれ、同義語や模倣の化鳥から逃れる苦しみ、汚れず拓心を切り刻んでいく克己心は、非情な世界なのであろう。それでも、「ほんとうにかきたいものを/知っていたと言うだけでは なんになる」、「みたこともない線分のなかで/やがてくる/ささやきを」、「ほろびることを、かくごしている詩を/底なしの紙に埋めてやる」のだ。 なみだ のぞんでもいない かなしさに さわったとき なみだは さざなみをたてながら すきとおったまま、かがみこむ あたりまえの ひかりのなかで にくまれも めいわくもかけない なみだよ ますます、こくなるくらやみに うずもれて たれの めにも、ふれることなく ぬれている・・・・・。 湿っぽくなく、透明に結晶した涙。光の中でかすかに振動し、闇の中へ入って埋もれていく。そこで始めて濡れるのか。個性を超越した深淵で、始めて共感ゆえ涙となるのであろうか。読む側も濡れてくる。臭いなく、乾いたまま....。見えぬはずの閃光。哀しみが、深い悲しみへと沈んでいく。もしかしたら、そこから、透き通って弾んだ新生の時空が誕生するのかもしれない....。 . 『あおもり文学の旅』 阿部誠也 北方新社 06.11刊 07.1.5 感想文の書けない書物だが、文学的には著書の短いあとがきに感銘した。陸奥新報に連載のためながら、県内のゆかりの地を時に妻子とともに同車しての旅は、とても文学的である。同時に、わずか1年5ヶ月で探訪し調べ上げた力量に感服する。 四十名の文士を取り上げており、うち7名についてはお名前だけしか知らない。その中の津軽地区にゆかりの御3人を以下に学習として箇条書きする。 沙和宋一(さわ そういち) 茨城出身。本名・山中勝衛。 1928年から9年間、桶屋町にあった古木名均の主宰する茶太楼新聞社に勤務。 1929年、四.一六事件で大沢久明、内山勇、堀江彦臓らとともに検挙される。 1931年、30枚の「木枯し」が東奥日報懸賞小説に入選。 1934年、<弘前創作の会>結成。提唱者の沙和を始め田中嘉彦、林専太郎、杉沼秀七らが集まった。 発表の場は「弘前新聞」の文芸欄であった。沙和は<弘前創作の会>を主宰しながら同紙に小説、評論、エッセイ、映画、演劇評など精力的に発表する。 1935年、「音」が東奥日報募集創作に入選。その後中央誌の『文化集団』に「石坂洋次郎と平田小六」を、『文芸評論』に「底流」「雪の記憶」、『早稲田文学』に「朝の媾曳」を掲載など目覚しく活躍。中央誌への作品発表は地元の文学青年たちを刺激した。 同年、沙和の主唱で「東北文学」が弘前から刊行され、編集責任者となる。 その後、工藤八千代(五所川原出身)と結婚。八千代は谷村貞子の筆名で「弘前新聞」などに小説を発表し、<弘前創作の会>の仲間であった。 反戦集会を開き、同人が検挙される。沙和は八ヶ月拘留される。 1938年、東奥日報社の見習社員となる。やがて正社員、編集部月間東奥部次長となる。 長編『北海の漁夫』(銀白出版社)、『民謡ごよみ』(六芸社、第5回農民文学有馬賞)を出版。 戦時中、思想弾圧で検挙される。要職にいた沙和は、読売新聞争議を支持する社説を載せ、それが論議を呼び、責任を問われ東奥日報社を退社する。 その後、大沢久明、内山勇らと「週刊自由」を創刊し、編集責任者となる。1946年に結成された新日本文学会青森県支部長に就任し、戦後の民主主義文学運動の発展に尽くす。 沙和宋一、ときどき目にし気にはしていたが、この書によって啓蒙された。 板垣直子(いたがき なおこ) 五所川原が生んだ女性文芸評論家の先駆者。 1896年、代々津軽藩の手代を務めた平山家の二女として五所川原市に生まれる。 1896年、栄小学校卒業後、弘前高等女学校(現・弘前中央高校)に入学。 在学中、校友誌に「色」「夏休み」などの短文や短歌を発表。 その頃、神近市子が赴任してきた。神近はアナーキストの大杉栄との不幸な恋に敗れ、小説や評論を書き、プロレタリア文学運動に参加している。 その後、日本女子大学英文科では、阿部次郎教授からドイツ文学への関心をそそられる。卒後引き続き研究科に残る。母校の推薦で東京帝大の聴講生となり、文学部で美学、哲学を受講する。女子聴講生としては日本で始めてであった。 英文学を始め外国文学を学び、日本文学の向上をめざす評論を志す。美術史研究の成果として、ゲオルグ・グロナウ著『レオナルド・ダ・ヴィンチ』を翻訳し、文筆活動に入る。美術史家で早稲田大学教授の板垣鷹穂と結婚し、著名も板垣直子となる。 最初の評論集『文学ノート』、他に『現代小説論』、『評伝樋口一葉』、『明治・大正・昭和の女流文学』、『夏目漱石-伝記と文学』、『現代日本の戦争文学』などの著作がある。戦前では唯一の女性評論家として活躍した。郷土の作家では石坂洋次郎、沙和宋一、平田小六の作品についても批評している。 板垣直子についてはほとんど知らなかった。刺激的であった。 最後に鳴海完造。郷土が生んだ高名なロシア文学者である。以前何度か鳴海完造に関するエッセイ等読んでいるが、普段ほとんど脳裏にない学者である。今度こそ、しっかりと修めておこう。 鳴海完造(なるみ かんぞう) 1899年に8人兄弟の4男として黒石市に生まれる。詩人・劇作家の秋田雨雀と口語歌人の先駆者・鳴海要吉の生家から二十メートルも離れていなかった。 黒石小学校から弘前中学校に入学。同期に詩人・一戸謙三、作家・石坂洋次郎がいた。中学時代にドストエフスキーの『白痴』を米沢正夫訳で読み、ロシア文学に惹きつけられる。それが動機となって東京外国語学校ロシア語科へ進学。同校卒業後、早稲田大学ロシア語科へ進む。ロシア文学者片山伸らがいたが、中退。そして帰郷、柏木農業学校の教師となる。 本県の先駆的同人誌「胎盤」を、一戸謙三、柴田久次郎らと創刊。 1927年、ソ連革命十周年記念祭に招かれた秋田雨雀とともに訪ソ。 海完はソ連に残り、レニングラードの東洋学院と国立レニングラード大学で日本語教師として9年間勤めた。ロシア文学、なかでもプーシキン研究に打ち込み、収集した蔵書は4千冊。 戦後帰郷し、弘前大学図書館に勤務。その後、同大学でロシア語講師を勤める。 晩年再び上京し、東海大学図書館に勤務し、その傍らロシア語を教えた。 なお、苦手な短歌の世界では加藤東離がいた。ほとんどお名前しか知らない。 加藤東籬(かとう とうり) 1877年に五所川原市松島の長男として生まれる。 高等小学校を卒業後、青森師範学校へ進むが病気のために3ヶ月で中退。翌年、東奥義塾に進学、が2年後再び病気中退。その後独学で思想、文学、宗教などを学ぶ。 同じ村で小学校教員をしていた和田山蘭を知る。 1906年、山蘭と二人で短歌結社「欄菊会」を結成、回覧雑誌を発行する。県内初の短歌結社であった。4年続き、14冊発行。こうして活字印刷による本県初の短歌雑誌「東北」が創刊される。 金子薫園(クンエン)の「短歌研究会」に入り「新潮」や若山牧水の「創作」などの中央誌にも発表。 社会主義思想に魅かれ、危険人物として警察から監視されたこともある。 山蘭は上京したが、東籬は郷里を離れることはなかった。 二年間村長を務め、その中にあっても歌作活動は生涯続けた。 因みに、他の3人とは、まず七戸の歌人・青山哀囚。生まれは一戸だが、父が七戸町の住職だった。哀囚も越前翠村(スイソン)らと短歌雑誌「東北」の創設者のひとり。七戸城址にあった尋常高等小学校での代用教員時代に、教え子として画家・鷹山宇一がいる。 次いで、人物月旦の典型を作り上げた鳥谷部春汀(シュンテイ)。父は寺子屋を開いた漢学者であった。早稲田専門学校で政治学を学び、帰郷後地方の政治運動を始める。その後毎日新聞の記者となる。さらにその後、雑誌「精神」や日本初の総合雑誌「太陽」の執筆者となる。大町桂月を初めて十和田湖に案内したのが春汀であった。 最後に、八戸を舞台にした作品の多い夏堀正元(マサモト)。生まれは小樽市だが、旧制八戸中学に2年在学、早稲田大学文学部は中退。父は東大卒の判事で、八戸市初の公選市長であった。正元は社会派作家だった。北海道新聞東京支社の社説部記者をしていた頃、藤原審爾らと同人誌「小説」を創刊、29歳で作家生活に入った。 以上、たいへん勉強になった。深謝。 . 詩集『時折風にゆれて』 黄河陽子 水星舎 06.7刊 06.8.1 冒頭の詩「少女」が、詩集全体のトーンの先蹤となっているように感じられる。「窓が風を叩きます/季節が移る時なのです」。ひとつの季節が完全に燃え尽くしたとは思えない。変容の序章であり、季節が移って何がかすかにしのび寄るのか。新しくもあり懐かしくもある何か。それを表現できるのは散文ではない。婉曲的にせめてそのしのび寄る空間を生み出せるのは、かろうじて詩法だけであろう。詩集の始まりである。「花の優しさ/根の我慢強さ/茎の賢さ」を植物が無言で知らせるように、季節の"移り"そのものがしのび寄るのだろうか。それは愛の中に持続する優しさのようなものかもしれない。その優しさとは、詩人が、夜の庭に植物たちと星影と風の"動き"が飛び交うのを、無言の言葉としてとらえる直観に潜んでいるようなものに違いない。この優しさこそ各々の詩のテーマであり、それが詩集の最後に置かれた標題作「時折風にゆれて」まで保たれているようだ。強風と雨に打たれ、朝露の冷たさにさらされる枯草。しかし実は、枯れ草に見まちがえられた一本の小菊であり、それは「授けられた生の途中」なのである。自然の生きようとする率直さ、それが優しさであろう。そしてそれゆえに、詩人側からの視線の優しさがにじみ出ているのはいうまでもない。 板戸に四枚の透明ガラスや東向きの窓に澄んだ光を観る詩人は、同時に、風の中に四拍子のピチカートで差の大きい強弱のメロディーを聴き分ける詩人である。古い柱の覚えのある落書きに雨のこぼれる音を重ね、悠久なな"時"の静寂を生み出し、夜明けに拡散する灰いろの星の灰いろの光にいたずら好きな妖精の息遣いを感ずる。これらも、優しさを包容するゆえのものであろう。優しさが、音となって響き、詩集のあちこちで音楽がきらめき奏でている。これもまた詩人の本領である。ただ、常にピアニッシモから始まる。 どれほどの年月が 過ぎ去ったのだろうか 静かに 短く 話していた そのころ 石よ 草よ 口を閉じてから どれほどの年月が すぎてしまったか ついに声なき原石や原木が、かすれ声を発する。祭りの太鼓が途絶えた遅い夜、小窓から細く吹く抜ける風が告げるように。そして、風が水が協奏し、霊気が小刻みに震え鳥や甘い声が交響する。ついに『交響詩』の完成である。 (やられたと思った。愚生も数ヶ月前から第二詩集、なかなかできず、当初の予定の内容ではない『交響曲』を構想していた。詩人と違って音楽のできない愚生は、逆に若い頃から詩で「交響曲」を創るのが夢だった。第9番で終わり、第10番は未完成という、完全に音楽的真似ごとだが、最近作った交響曲の簡易データを膨大な資料と付して。しかし、いざ創るとなると、習作の意味の第0番、前古典派の母胎としてのシンフォニア、あるいは第3番あたりにせよ、まずどう始めるかからして難題だった。そうか、ファゴットのソロから始まったか。昨年の詩朗読会で既に発表していたのか。愚生、もしかしたら間接的にその影響を受けていたのかもしれない。) 流石なものである。第一楽章、さりげないメロディーに、素早く後に従い次にゆるやかに続く。歩き出し、ついて行き、大勢の話し声、独り言、それらが大木の小枝を吹き抜ける風となり、胸に愛を響かせる。悲しみを忘れようと。第二楽章、ひとが生み出す美しいもの、内に行き来する小人の繊細さ、瞬間瞬間にふるさとの断片を精一杯集中させ、一気に仕上げようと邁進してはつまずいて立ち止まり悩む、そしてついに完成の歓び、それも束の間、暗い霧がしのびよる、静かに夜明けが訪れても満足は晴れず、荒々しく暗い雲が動き、海も陸も身震いし、安らぎの光がすべて消え去る。第三楽章、かすかに伝わってくる落ち着いた気配、静かに眠るときが来るのを暗示するかのように日が昇っては沈む、贅沢な光や闇に柔らかく覆われて、最初の、故郷という大地のファゴットが聞こえてくる。交響詩だ。 ことに声楽も詩人の得意とする領域。バリトンに、同時に万物の耳をそば立て、満天の星の震えを体感する。詩の情感を音楽に完全に載せることができるのだ。それは、音なき、沈黙の舞姫にさえ共鳴し、内なる響きを共振させる。舞いは、「限りなく薄い零度の夢を水平に掬う」のだ。さらに、画像の女の微笑みにも、息づかいを、その女の耳を通して見えない羽ごろもが包むのを観音するのである。 しかるべき安穏の美、しかしそこには同時に必ずしかるべき存在の寂しさが付き纏っているようにも感じられる。 大地に抱かれる遠い声のひびき 空に続く窓の 大気がふるえるふしぎな力 何百年何千年を経て いまこの瞬間にようやく… 宝石が輝くようなその瞬間瞬間、まさにいまこの瞬間。悠遠な過去があるからこその瞬間、その命。 なのに、いまだ銃撃戦など、人の命や地上の生命など全く考えていない世界がある。その憂慮も、詩集全体に流れていることも確かであろう。アジアアフリカの民族紛争、あるいは世界の宗教戦争がいまだ続いているのだ。合衆国の軍事的政治的驕りが、なおさらに悲劇を深刻なものにさせているように考えさせられる。世界史的視点、窓からそそぐ小さな光に、遠大な内的世界が秘められているのだ。戦時中、大連市で過ごした詩人だけに、行が少なくともその訴える力は強い。郷土では稀にみる大陸的なスケールをもつ、草分け的存在の女流詩人。高木恭造を思わせる、後続の郷土の詩人たちにますます畏敬の念を深められつつある、日本詩人クラブの永年会員である。そのような意味でも、特に『露天商』は時代さえ超越した世界詩に通ずるものであろう。 昼下がりに チェンピン一枚だけの食事 五十半ばの中背細身 ピーナッツをつまんではいけない 売り物に手をつけるな となりの にわか露天商に教える 午後には骸になってしまうとは 金を払わぬリンゴ一個のために ソ連の兵士の自動小銃に倒れた 朝もやのなか 道端のむしろの傍で おさげ髪の娘が泣いている 卒塔婆が女の死体を抱えて表の入口から入ってくる『訪問者』は、より文学的である。上がりかまちに下ろされた死体は、髪が乱れ腰から脚は硬直したまま床に伸びた。卒塔婆は細く女の声ですすり泣く。二〇〇三年十二月四日朝六時。ちょうど一年前の二〇〇二年十二月四日は、女流詩人T・K子の急逝した日だった。ようやく、卒塔婆の姿で自分自身を運んで来たのかと怪訝になる。明けて翌日、従姉妹の訃報があった。十二月四日ちょうど朝六時。詩人はこの出来事に、永遠の空間を見出し、そこに耳を澄ます。 詩人の内には、涸れるどころか痩せることのない輝点が永遠に宿っている。すべてに平等におだやかに対峙する優しさの内側には、いつでも放射することのできるその言葉が静かに待機しているのだ。台所から納戸まで、あらゆるものに自らの<授けられた生の途中>そのものを瞬時瞬間所与できる生来の詩的脈打ちを体内に保持している詩人なのだ。敬服の至り、としかいいようがない。郷土で、このように詩について自由に論ずることが許されるということは実に幸せなことであり、そうさせてきたのが黄河陽子氏なのだ。 . 詩集『大銀杏の下を』 工藤浩司 北方新社 06.4刊 06.5.13 冒頭の標題作を読んで驚き感動してしまった。次の「時計」も、更に次の「四月の庭で」も同様である。冒頭の詩の感慨のまま、一編一編、同様の感慨のまま最後の作品まで続いたのは、これが最初かもしれない。すべての作品が詩らしい詩であり、読み易さは柔軟性を感じさせ、かつ内容的に掛詞的な大きな転換あるいは比喩が潜み、すべて佳品なのだ。どれも日常あるいは現実生活に根を下ろしながら、詩作品として豊かな感性が広がっており、卓越した想像力が膨らんでいる。一種の、天性かと思わせるほど神技的な作風であり、瑞々しさが横溢しているのだ。優しさの中に詩的情感が湧き上がり、著された詩行以上にふくよかな情景や心情を重ねていく。 父も母も祖父も祖母も とっくに大銀杏の下を左に折れて 畑一枚の向うへ行ってしまったから お盆の夏の暗い夜に 火を焚いた わたしの前を走っていく時間と わたしを追いかけてやってくる時間のはざま ちょうど畑一枚の広さの いのちの時間に灯す 篝火のように この冒頭の詩「大銀杏の下を」で三度用いられる「そんなことだろう」の一行が、まるで生きた含蓄のあることばに思えてくるから不思議だ。"そんなこと"とは古来からの"風の道"なのであろうか。だれの命の時間にも始まりと終わりに大きな余白があるように、一日の時間の始まりと終わりにのはみ出したところに、夜の鏡があって無数の白い影が行きかっているように、"そんなことだろう"。 むかし 茅葺きの暗い部屋で 柱時計はゆっくりと時をつむいでいた。 あの時代 時間だって きっと手巻きだったのだ そこから あしたやあさってが 少しずつほぐれて だれもいない部屋の暗がりに落ちてきた いずれも物語風に昔日を回顧、いや懐古しながら現在に結び付け、遠い過去から何度も往復しては詩人の人生を物理的な時間よりもずっと長いものにしている。文学人の得意技に違いない。時間はゆっくり流れ、この詩人がその中を銀色の自転車に乗って自在に"走る"ようにしばし振り返り、時間そのものがまるで生きているように思えてくる。 読みながら愚生もおのれを追懐してしまう。昭和三十年代に農家に少年時代を過ごした愚生。茅葺屋根のがらんとした暗い居間。遊び疲れて家に戻り、大の字になっていると柱時計が鳴る。両親は田仕事、兄妹はそれぞれ仲間とどこかで遊びふけっている。誰もいないことに突然不思議さを覚え、そして孤独感に襲われる。皆はたまってどこかにいるのでは。家族写真の中に、自分だけが移っていないような非在感。淋しくなり、人恋しくなる。ほんとに何もない家。外に飛び出すと、目がくらむほどとても明るい。そういうときに限って、兄妹や仲間を探し廻っても誰も見つけられない。ようやく誰かにめぐり会えると、口元に笑みがこぼれるだけで言葉が出ない。その時の安堵した気持ち。この詩集は、そんな安堵感をたくさん与えてくれる。 堅く重い雪が消え残った 四月の庭 折れた枝が残った雪に突き刺さり 林立している異様な光景 それでも四月の陽ざしは あっという間に雪をとかした 枝々はようやくしずかに土に体を横たえる ・・・・・ こんなふうに折れた枝を拾うのは 父や母や 祖父や祖母の 私のいのちにつながる者たちの 枯れた骨を拾うようで どこかせつない いま、あれからどこをやって来たのだろう。あれからどのくらい眠っていたのだろう。かくれんぼのオニが見つけてくれず土臭い藁の匂いの中で眠りこけてしまったが、それからだったろうか。それとも、少年の夏の日、日が一日川で泳いで昼時に大銀杏の下で眠った、その時々からだろうk。いや、夕立が過ぎた空の虹の下を、明るい方へと、懐かしい声のする人々へと駆け出し、それからずっと駆け出してきたのだろう。約束されたはずの時間から、道から、傾きずれて進んできたのだ。言葉を変えれば、ひとつの痛点、例えば、裸木の枝先にひっかかり吹きっさらされ生きている時間、そこから溶け出し溢れ出てくる時間なのだ。 何ひとつだいじな言葉を受けとらぬまま 美しい瞬間も映し出さぬまま どんな秘密も明かされぬまま あいまいな景色と時間の中を 今 走っている うつらうつら眠りかけては目をさましながら、胸の空の奥深く、はだかの魂を透過していく風とともに、灰色の道をそこまでも辿って走り続ける。でも、どこから来てどこへ行くのか。暗がりも果てしなく続く。走るのは、懸命に生き延びるためである。走るからこそ、相対的に時間はゆっくり流れるのだ。詩人の時間は、幼い頃、ひとりで砂丘の向うに歩いて行き海と出合った時に誕生したらしい。この詩人の時間とは、 たれかが一度よじって 両端を貼り合わせて しまったメヴェウスの輪 とたんに消えてし まう面と裏 昼と夜 生と死 開けることの ない闇 なのであろう。それは、滅びつつある蛍のように、決して発光することのない胸の鼓動なのかもしれない。 この詩集は、内的時間の運動を見事に具現し、現象学的な"時の詩集"といえるのかもしれない。時間のつながりと、伸縮、そして裂け目を追求している。だから、時間におきざりにされることは、本質的なおののきを呼び起こす。いつしか、それは死を、つまり時間の無化、遠い過去への遡行を意味することになろう。 まっすぐ海まで延びる道に、銀色のフナの屍体が置き去りにされている。腐蝕していく肉にハエが飛び回る。白濁したまま見開かれた目。沈黙した空の深い青さをみつめたまま。少年の詩人は、それをじっと眺め続ける。一緒に歩いてきた母は、「いつまで そんなものを見てるの/ほんとにおいて 行っちゃうよ」と先に進む。 光の影がしきりにふる時間のそこに あきざりにざれる 急にたかまる潮騒と胸の鼓動 あわてて白濁したフナの目の青さの中を 走り出す あれから数十年 母は日におとろえ うすい狂気の影をまとって ある夏の日 傷口のように開いた時間の向こうへ 白い点となって消えて行った 今 さくらの花が散りはじめた城跡の道を わたしは歩いている 白い花びらとうすい光がわたしをつつみ 白濁した時間の傷口ふかく 青い沈黙の影をいくえにもまとって はるかな いのちの時間の道を (「おきざり」) 標題作と同様の小題を持つ以上の第一部の、追憶にある大銀杏は、それは遥か遠くから到来する、しかしそれは常に内奥から響いてくるような、淡くも持続力のある樹木だが、第二部の邪魔になったため伐採される庭の樹木は、目睫的で具体的である。漸次的に時間時間と共にあり、その連詩のような構成は物語的である。実に上手い配置である。瞬時瞬時と、時間の流れ、そして時空の裂け目がうまく連動されている。表現も生活的でありながら実に詩的でもある独特な魅力を放っている。特に「心 一点」と、「せつない」「あした庭師がチェンソー持ってやってくる」に感銘してしまう。「そこにずっと立っていた」は、切り株を介して先の「おきざり」の詩へと連結しはしまいか。その庭の樹木は、詩人でもあったのである。 それは、時代の終電車に乗せられた、第三部の私でもあった。闇に延びる遥かな時間に運ばれていく。食い散らかしてきた日常の時間であり、誰かがかじって捨てた、生まれた時からずっと思い出せない形象的時間なのだ。既に始まっていたのだ。風の道を自在に操る鳥だって、ついには死の重力に捕らえられてしまうように。剥ぎ取られたジグソーパズルの台紙だけの、背景の闇に飲み込まれた時間へと。 獣には森を行く道があり、風にも野を行く道があるように、行くべき向こうがあるのだ。忘れ物を取りに行くかのように。向こうから、風が運ぶ、遠い地球の、音が聞こえて来る。 . 詩集『ひとりぼっちのおとうさん』 渋谷 聡 漉林書房 05.12刊 06.1.25 渋谷氏の第5詩集。すべて初出のある28編。同人である地元の詩誌「阿字」と田川紀久雄氏主宰の中央の詩誌「漉林」での初出が中心で、他に「文芸あおもり」に2編、「北の街」と「陸奥新報」に各1篇ずつ。前書きや後書きはなく、さっぱりとした詩集である。 詩は個人的な内容が多く、一般人からみれば教師という恵まれた境遇にありながらも、どこか自らの人生に満足していない内奥が吐露されている。「たかが労働者じゃないか」など勤労者としての正直な発言であり、例えば「花咲く頃の空の青より」など、先例追従の形式主義として上司や教育のあり方への批判も読み取れる。夏休みや冬休みがなくなり、ますます多忙に追われている教師たち。年中、休む暇がないであろう。一時間一時間に情熱をかけて働いているはずである。疲れきった教師たちが多いのだ。文科省はいったい何を考えているのだろう。機能主義的な功利主義の観点を捨て、教育の真の意義を再考してもらいたいものである。ゆとりがなければ充分な教育はなされないであろう。行き過ぎた組織化と官僚化も、教育の本来の目的を阻む。多くの詩は、そのような共感を呼び起こす。それだけに、少なくとも、詩人自らの子どもたちを、家庭を愛し重んじていることがひしひしと伝わってくる。海辺での砂遊び、雪原の波での凧あげの詩など、とても情景的でもある。子どもたちを「生きていることを見つめ続けることが父の最大の仕事なのかも知れない」。たぶん、実際には教育現場でもそうであり、子どもたちに好かれている先生であろうことが推測される。朗読会等での幾度か遠方からの拝見の他に、一度だけちょっと対話をしたことがあるが、明るさを持つ恰幅のいい、ギターの弾き語り詩人である。鳩や烏、田螺、蝸牛、蚯蚓など小さな生きものに対する情愛も深い。そして各々の自恃を代弁する。 セメント文明に焼かれ 人間に潰され 土龍に食われた のたうち踊っても 龍のごとくからだを捻っても 死ぬときは死ぬ 土が死ぬから 地球が死ぬから 切られても切られても たとえ アスファルトの上で干からびたとしても 亡骸は 蟻にあげる ・・・・・ できるだけ 見ず 聞かず 喋らず 突き進む隧道は 我のない道 誰が何と言おうと (『蚯蚓の決意』) そこには自ずからすべてのものの平等感が生まれている。詩「あなた、そんなに偉いの」にそれが端的に表現されていよう。そして、雪の下の沈黙し続ける小石、川底で流れに任せますます丸くなる小石の存在までに到達する。すべてが詩人の心情の投影にもなっていて、それは幾分卑下の調べであるが、謙虚という名の頼もしい勇気なのだ。 だからこそ、自動車音や人口の建造物がかつての風景を変え、生態系を破壊してきたことに対する怒りは、静かながら深いものがあり、心底から文明中心主義を批判しているのが看取される。それでも、詩人とともに、生きものたちは怯まない。死をしっかと見詰めながらの確かな生があり、詩人は遺伝子レベルまで遡及して宇宙をつなぐ。 また、次のような箴言に近い詩句も多い。 空の青は何も無いこと 大きければ 見えなくなる ・・・・・ 時 長ければ 計れなくなる (『見えないものがそこにある』) なるべく明日は来ないように 今日がもったいなくて いつまで生きられるか (『心ここにあらずや、四十の春) それにしても、『うたう生命体の魂から』と『遺伝の地図』は現実的でかつ実存感の濃い作品である。身に降りかかった世間によくありそうな運命を、スケールの大きな詩へ昇華させている。妻の宇宙に宿る生命、生命の宇宙への帰還、宇宙からの生命の系図など、普遍性の高みへ向かって構築している。この詩集は、日常的でありながら全体的に、いつも生と死が同等に主題となっているといえよう。 最後の詩で、平易な言葉で、暗喩的に人生の哲理を語っている。 水に削られ コロコロ、と 川底を流れ ゆっくりと下りていく 丸くなれば水が連れていってくれる 川を上ろうなんて考えてはならない ・・・・・ 大声を出してはいけない じっと 黙して 状況を見守ることをすればよい ・・・・・ 勝ちたい、などと 欲を出してはならない 時が過ぎれば状況は変わる ・・・・・ いつかここは滅びる 滅びるまで ここに 生かされていればよい (『ぼくは石ころ』) . 『一輪咲いても花は花 葛西善蔵とおせい』 古川智映子 津軽書房 03.6刊 05.12.30 葛西善蔵の、鎌倉でハナと出会ってから死までの伝記的小説である。葛西作品の事実性や史料を猟渉し、また舞台あるいは俎上になっている地を探訪しての努力の賜物であろう。優しい文章であり、読みやしく物語としての読む側の流暢さを損なうことなく、小説世界の中に没我にさせる。表現上変に衒うことなく、叙述も平易であり、会話も日常的である。一年間に渡り週一回の五十回、街の新聞による新聞小説のゆえもあろうが、むしろ著書の人徳のよる文体なのであろう。平叙でありながら、肌にぬくもりが伝ってくるような不思議な力を秘めている。 1932年生まれで弘前中央校、東京女子大の日本文学科卒の著者は、文科省直轄の国立国語研究所、高校教師を経て執筆活動に入るという、文章の専門家である。この書は装飾なく無駄のない堅実な文章で占められている。かつ、ラジオ放送の連続ドラマや舞台化された作品も持つように、万人に愛される標準的文体でもあるといえよう。客観的で共通的な、篤実で模範的な文章を構築するのは、大変な推敲力と努力を要すると思われるが、著書は長年にわたってその才能と技術を養ってこられたと推測される。 それにしても、葛西の小説を書くことへの執念はすごい。書けないとき飲酒し、奇声を発して部屋を徘徊する。時に竿を取り出しての釣りやゲートルを巻いての登山の真似事をする。そして、ハナがどんな状態であろうと、ハナが煩わしいと旅に遁走する。少年時代、ゴッホのテオのように忠実な弟勇蔵と一緒によく登った碇ヶ関の三笠山を思い出している。葛西にとっても、故里は臨終まで忘れることのできない安住の地なのだ。 原稿料は焼け石に水であちこちに借金しては逃亡。不潔な貧困、不衛生な病苦の作家。そんな葛西の、それでなくとも妾に過ぎない、良心の呵責にも悩みながらも、葛西にどこまでも尽すハナ。葛西はハナのお蔭で書けた、外見的だけではない、内容的にも書けたのだ。暴力を受け、嘲笑卑下されながらも葛西を信頼した。寄り添って八年。「花、一輪か。一輪咲いても花は花。ハナ、お前のことだよ」。葛西最後のとき、雨降る痩せた狭い庭に、淡い水色の紫陽花が一輪、全てが薄暗く沈んで見える風景の中で、そこだけが仄かに明るかった。著者が葛西について書こうとしたのは、ハナのためのような気がしてくる。ハナの娘二人はどんな生涯を送ったのだろう。葛西全集により出版社からの月々の支払いはいつまで続いたのだろう。いま、葛西全集を発刊しているのは津軽書房である。 石坂洋次郎も葛西に対し弟子として献身的であった。葛西の弘前滞留の事態は、石坂の『青い山脈』でも具体的に知れる。他に、送金してくれた浪岡の妻の実家平野家、出版社の編集者で同郷の佐々木、信州屋の丸山老人、家庭を捨てて恋仲と出奔した嘉村磯多らの献身振りと葛西の偉業への慧眼が光る。 書くという行為。利害打算なく、身を削っての壮絶な作家魂。刻心鏤骨の完璧主義。頭の中で何度も練り、万年筆で一回勝負する。直しのない綺麗な原稿。離れ業のような緊張感を受ける。体調が悪いとき、誰かが口述筆記する。途中、何度も中断し、無関係な椿事があっても、長い中断であっても、正確に前の続きから始まる。 「作家は人生観を持たなくちゃならん。その人生観を表すのが小説なんだ。生活に裏打ちされた人生観だ」。そんな姿勢に深い敬意を覚える。しかし、自分の恥部まで抉るのはよいが、身近な人たちまで言及するのは、常人には真似できないことであろう。広津和郎が憤慨するのも道理であろう。葛西の臨終間際にわざわざ謝罪を請いに出るのは非情だが。そのようなことを覚悟しながらの、私小説作家というものの性はやはり貧しいものに違いない。 「作家は自殺したがる。安易な道だ。死ぬほどつらくとも、自分と向き合って書くのが、作家魂というものだ」という主張にも頷ける。どうして作家は自殺したがるのか。そして、葛西にしても、どうして自殺に近い破滅的な生き方を選ぶのか、常人には理解しがたい。喘息、神経痛、肋膜炎、最後に肺結核と腎臓炎で、四十二歳で死去。四十二歳である。なのに、なんと多くの短編を残したことだろう。 ところで、この著はあくまでも小説である。実話に基づいたものであろうが、著書にとっては著者の小説作品なのだ。葛西とハナの出会い、初期の献身と愛慕、地震のときのハナが置いた卵が転がって救われる場面など、心深く残る名表現であろう。 古川智映子という作家、市立図書館に幾冊かの著書が並んでいる、中には研究書も含む、知ってる人は活字で以前から知ってる大変な方だが、ここ郷土において、一般の方には初めて紹介される一冊であろう。この書はそれこそ、この閉ざされたような狭い郷土にも咲かせてくれた、<一輪の花>であり、輝く花である。 . 詩集『ゆめ旅』 一戸郎 青森県文芸協会 05.8刊 05.8.28 詩集は持たないと心に決めての、長年詩作されてこられた詩人。それでも上梓と薦めた写真の中にしか残っておらない先輩同輩詩人たち、身辺整理と同時に彼らの写真を焼くことにして上梓を決断されたようである。詩に対する執念を強く感じる。傘寿。標題作は冒頭にある。 ぼくのテーブルの片隅に 西アジア山岳地帯の荒れた野が広がる ・・・・・ 限りなく静寂の棲む地はやさしく 歳月の遥かを辿り 哀愁がとぎれなく余韻をひく地 ・・・・・ 住みたい風景の知らない夜を立ちつくし 遅い 日の出を待っている 旅の窮極は放浪の 終焉は白骨を撫でる風だけなのに 皮膚をきて 遠い日のままの遠い目をした咄 思いばかりの放浪者 君夢想のひとよ 静かに共感を覚えさせる深い詩である。表現も実に重みを伴った、また特有な言語世界を構築している。「住みたい風景の知らない夜」や「遠い日のままの遠い目」など何度も反芻し、それなりに意味を把握しながら、様々な解釈が折り重なってくる。イメージが壮観に重層的に広がっていき、かつ内面へと沈降する。読書、芸術鑑賞は、すべてこの詩のように居ながらにしての内面的な放浪の旅であろう。現実的には不毛な、机上の夢であり、しかし形而上へと深遠さと普遍性を孕んでいく。人生もまた、そのようなものに過ぎないこと、いやそこに意義があることを悟らせてくれる。宗教性を剥ぎ取った仏教の裸の真理を照明し、すべては只管打座の世界に森羅万象を写しているに過ぎないこと、すべては虚像であることを諭す。盆栽も自然も同値なのだ。脳裏にだけ世界を構築し、しかしいずれ消え去り、零度の存在だけが残るという哲理なのだ。 次の「子雀の咄」がその具体例となっている。儚き死。それへの救いの行為もまた儚きもの。飛べない子雀の短いチュン生。こころ温まるヒューマニズムが効果的であり、老僧侶の人生のような残り少ないだけに生ずる底光りのような仏理を覚える。具体例とは、畢竟些細な事になってしまうこと、些細なことに真理が詰まっていることを諭す。続く「赤蜻蛉」も同様の作品である。 小春日の日溜りを 幻想の小人たちゆらり揺れ 扇のような小春空に 楓の細い枝が刺さり 紅葉の名残りの葉がまだ別れを終わらない めぐる四季 殊更にやさしい一刻の晩秋を 一夜が初冬をめくった 小雪混じりの氷雨が降る。びしょ濡れた夏網戸に、貼りつくように止まっている赤蜻蛉。脚が絡んで落ちないのだろう。娘がゴミを払うようにちょんと弾くと、氷雨の溜りに落ちていく。「来し方をからめ/夢うつつのように生き/日により気により/忘れた本のページを捲る」。蜻蛉は確かに位置を少し移している。翅は開いたままで動かぬが、生きているのだ。枕の上に置き、テッシュペーパーで翅を吹き、顔や細い首の水滴をとる。やがて小刻みに翅を震わせはじめ、光の方へ向かって大きく翅をふる。小さな命への深い慈しみ。のちのち、ユーモアを仄めかしながら実生活を歌う詩の中に特に共通するものが表現されていく。 例えばそれは、逆説的でもあるが、二百億年遥かビッグバンから核融合しながら飛来した、稲妻のように銀鱗を煌かした目刺によっても語られる。そのような形而上学的夢は、岩走る三態の水のようでもあり、生が誕生する性的な魔鏡でもあろう。全ては眠りの中でのことであり、草原にたくさん転々とする鬼火に惹かれて白昼夢に生きるようなものだ。幕閉めに、逃亡していく四季のある日、妖しい小さな母湖の湖心のほとりで、音もなく水面が花のように花ひらく。そして、その水の面が夢の最後の生を吸収する。 長い詩が多い。始めのうち多少漢文調を感じたが、その特有の巧みな表現方法に慣れてくると、それが内容の深さゆえのものであることが理解でき、表出されるものが自らの中にも顕現できるようになる。地元の詩集の中では難解な詩集の部類であろう。多分に象徴的に読める詩が多い。そして重厚な詩が多い。なるほど、若いときエリオットや荒地派に夢中になっていた詩人だった。ヒューモアも、それゆえに切れがあり、実に効果的である。そして何よりも、その深遠には愛が潜んでいる。次の詩が最後を飾る。ほとんどの作品が紛失した頃の五十余年前のものだけに、回帰的あるいは通奏低音的なものをも感じる。 レースを編むのは愛を編むのです 遠い内部の はかない芯の針先に 思いの糸をあやどりながら レースは己を編みこんでいるのです ・・・・・ 孤独の目まいや 千の乱れを アラベスクに あるいはかなしく幾何学的に レースは思いの糸玉をくるくると廻し うつむきながら 虚空に編みゆくものだから 温い毛織のように空間をつぶせない 叶いがたい空間を いくたび思いがこぼれ そのように時を流れるのことだろう ・・・・・ 思いの糸がよじれてしまい 遠い内部に無の点景が沈むとき そのとき 愛よと呼ぶのです (『糸編(レース)』 愛を編む。針先には何も見えない。しかし、つぶすのではない、生かしたふんわりとした空間がある。それは、愛をつぐむことでもあろう。編んでいる悲しい幾何学なのだ。"かなしい幾何学"、すごい言葉である。生成流転する年齢を超越した"言葉"。"かなしい幾何学"は、冒頭の詩の、机上の盆栽を想起させる。内面的な夢の造形なのだ。人生の歩みとともに、幾何学から造形へ。時に、日常において思いがこぼれ、それがユーモアとして微笑む。不変なのは、遠い内部なのである。そこで意識があるいは原意識が無の点景として沈むとき、逆に詩人の眼となって世界を鳥瞰する。小さな命、小さな造形自然に、あたかも巨大な釈迦がそうするように、詩人の愛が注がれる。まるで人々の現在進行形の人生を、詩人が鳥瞰しているように感じられてしまう。その人々の中に私もまぎれているのだ。読む私は、夢の内部へと読まされているのだ。傘寿の、"言葉"さえ超越した畏敬を覚える執念。頼もしく、また凡夫を鼓舞してくれる情感でもあろう。 . 詩集『オパール色の交差点』 楠美明子 私家版 04.9刊 05.2.27 詩集『下北・未完の旅』 佐々木髙雄 企画集団プリズム 04.11刊 05.2.28 共にまず標題からして対照的である。そして性別、知名度、取り扱うテーマ、片や外向的で片や内面的など極めて対称的なのだ。表現方法も、散文でエッセイ的とオーソドックスでまさに詩の香を放つ、と対称的。日常的コラム的で飄々とした一方、孤独で叙情的。 逆に共通点も見出せる。詩集としては両者高齢での余技的第一詩集である。余技に違いないだろうが、人生の年季からくる文章は、軽くも説得力に満ちている。 楠美氏の詩集は、2001年に30年ぶりに帰郷しその後5年間にまとめたものであるという。5年前には『暮らしのスパイス』という著書を上梓している。文体は"あいつ"と呼び強気であり、堂々と津軽弁を用いて強情で、頼もしい詩魂である。ピアノを習う他に女子中学生の頃からませて映画が好きで文学書を読み始め、女子高時代は五能線で弘前のミッションスクールに通学しピアノに励んでいた。「さざ波Ⅱ」などで1960年代はヒッピーガールであったことが推測される。時に「初夏の朝」などで少女に帰っては、「夏の食卓」で現今の気さくな夫婦仲を覗かせてくれる。だが全体的に、人と物との価値観が逆転していることや新規な事柄にだけに騒ぐマスコミに対してなど社会風刺が効いている。皮肉っぽい表現は、ある意味で女性ならではの同じ高さの目線からゆえ発言に真実味が高い。日常の中での警句集となっている、とも言えよう。お洒落が好きな"シンデレラババア"と自称し、ヒューモアも心得ている。 音楽大学時代は東京で過ごし、昭和40年代後半はピアノ教室の講師をしていたのか。昭和50年代は仙台だという。自伝的要素も強い詩集だが、陸奥新報のコラム「冬夏言」のように随時随筆的エスプリを垣間見せてくれる詩集である。 この高名な方が、詩を書かれていることを初めて知った。新聞社の社長だから、文筆活動は職業であり、編集局文化部長も歴任しているから文章が得意なのは当然であろう。むしろ驚いたのは、十代より詩を書いていることである。いや、だからこそ文化部長の椅子に座ったのだろう。昭和9年生まれ、街の出身であり、時々青年時の噂を文学の酒席で耳にはしていた。愚生ら愚民には推し測ることができない大変な名士である。 初めての無銭旅行が昭和二六年の高校二年の時で、下北は詩人のアルカディアとなり、翌年から詩作しだしている。それが十年ほど続き、勤めてからも詩作は続けているという。愚生は怪しい符合を覚える。昭和二六年は愚生の生年、詩作を始めたのが高校三年、妻との最初の旅行は下北だった。以来、妻との旅行が人生最大の喜びとなった。 詩集全体から受ける印象は、どの詩も上手く処女詩集とは思えないことである。詩行がもう熟練の境地にある。長年にわたり新聞記者であったから当然といえば当然のことだが、それだけではあるまい。詩は記事と違う。散文とも違う。多忙な身にありながら、これまでどれだけの詩を書いてきたのだろう。多分、量は多くはないだろう。この詩集には二十編の詩が収録され、うち二字熟語標題が十五編も占める。苦悩、不在、眩暈、風紋、沈黙、足跡、錯誤、幻影、陥穽、血痕、残響など、これだけで詩の表現の仕方や雰囲気、そして内容までが見えてくるような気がする。愚生などは読みたくなる標題である。因みに三字熟語が四編である。 本州最北の半島、その岬、厳寒のひなびた小さな漁村に詩人の孤独が融合する。固く殻を閉じたままの、ささくれだった村。石塊だらけの番屋がある浜。潮風のみならず砂混じりのざらついた風が吹き、雨にえぐられた粘土の道。村の端から端までの一本道。静観的に、暗灰色な色調で内的モノローグが展開される。静寂な海は決して明るくはない。むしろ貧相で昏い。夜はひときわ夜の色を濃くする。詩人は、なぜこんなにも陰鬱な風景を求めるのだろう。詩人自身の心象風景なのかもしれない。「足下の小石をポケットに入れると/いきなり寒さがつきあげてくる」「暗いのは僕の思惟だけか」。いつ頃の作か知らないが、青年の孤独が響く。文章の秀でたこの詩集にあって、珍しく簡潔な次の、海鳥に自らを写像した詩が鮮明に浮き立つ。 揺れるにまかせているのは あれは きっと 辛いことなのにちがいない そんなことでしか おまえたちは おまえたちの苦悩を 表現することができないのか (『苦悩』) 形があるだけの人と 形があるだけの暮し いや 訪れた僕にしても 形があるにすぎない僕だったのだ (『眩暈』) と、女々しくなるような心情にも陥るが、なにせ日本の著名な方々と何度も対談し、紙上で幾度も披露されている御仁である。繊細な感受性の中に、硬質な何かを感じさせてくれる。愚生も、職場主催の何度かのパーテーで上席の方に幾度も拝見している方であり、ただ残念ながらこちらはいつも舞台裏で黙し控えている超脇役、いやほとんど準備係の役さえなかったが、とにかく大物な方である。それだけにこの詩集によって、若いときから保持し続けている詩人の真に大切にしているものが伝わってくるようにも思われる。 楠美氏と佐々木氏。初めて知ったお名前、ずっと昔から耳に胼胝ができるほど目にするお名前。偶然のことだが、多くの面で極めて対照的な詩集を読むことができた。ともに歴とした詩集であり、詩とは何か、詩人とはどういう人間か、自分なりに思考の反省を促すことができた。 . 『生誕百年記年 石坂洋次郎集』 石坂洋次郎の会 非売品 2000.10刊 05.2.6 郷土が生んだ国民的作家石坂洋次郎。2000年で生誕百年ということは1900年生まれということだ。1986年没。当然訃報を紙面で知ったはずだが、その時傷心を覚えた記憶はない。むしろ、心残りなく大往生されたのだろうと思い、その偉業に対し改めて敬服を抱いたような気がする。当時、まだ石坂文学を読んだことがなかった。未読を気にしているうちにご本人が他界してしまった悔しさは、多少感じていたかもしれない。そういう悔しさは何も郷土出身の作家だけに感じるわけではない。日本のみならず、世界の作家に対してさえ覚える。昨今ではサガンが記憶に新しい。それまであまり関心がなかったサガンが読みたくなったのだ。石坂文学に対しても似ているかもしれない。昨年初めて『青い山脈』と石坂文学についての『山のかなたに』を読んだ。 街の文学の重鎮、<石坂洋次郎の会>会長小野正文氏は、本書序で、石坂洋次郎没後十周年として、女優の吉永小百合氏と映画監督の西河克己氏、講演者として長部日出雄氏を招き市民会館で<いつまでも青春>を開催したイベントについて触れられている。その時、吉永小百合氏は謝金を受け取らず、生誕百年記念に役立ててくださいと仰ったという。そのご厚情で本書がなったことを伝えている。また、小山内時雄氏が、人々に読まれた作家だけに単行本、文庫本、作品集および全集シリーズなど多くの刊行があり、添削に厳しい著者自らも加わったらしく表現に変異があるが、『短編全集』本の本文を尊重すべきであり、本文批評という地味な作業が重要であることを強調されている。 本書には、旧制弘前中学時代に発表したものと短歌雑誌「ひとみ」に収録されている短歌21首と、弘前高校文芸部誌「のろし」に掲載された随筆『文学の地盤』も参考資料として併載されている。短歌では時に「石坂牧星」という筆名を用い、「立小便するうつけ者みたりそが上に星さんらんと輝きており」他一編、星を歌っている。「立小便」のこの歌、髙木恭造の詩を思わせはしまいか。月ではなくこちらは星だが。しかも方言を用いている。「うたて」は3首に用いられている。確かに「うたてし」は古語ではあるが、方言として用いているよな気がする。「をめく」もそうだ。それにして「勉強すと集ひし三人あなうたてそばな食ひそと室を出づるも」は、ありふれたことながら実に愉快な首である。短い文章の『文学の地盤』は、後年、中学時代偏食的にただ小説ばかり読みふけっていたことを後悔先に立たずと反省し、文学の地盤には万遍なく耕された常識的な社会生活が必要であることを後進の若い人々にアドバイスしている。 作品として、昭和二年に「三田文学」で発表された処女作の『海を見に行く』と初期の短編2篇『炉辺夜話』『キャンベル夫人訪問記』、そして葛西善蔵との関係を表出した『金魚』の4篇が収録されている。斎藤三千政氏の解説によると、北原武夫は、『海を見に行く』で既に石坂文学は「作家が取り組むのは結局は道徳の問題だ」という文学とっての根本問題を扱っていると評価したという。また、石坂は葛西善蔵に私淑し初期の作品は善蔵風の<私小説>的傾向が強い。長編小説『若い人』の原型である『金魚』は、後年の数多くの成功作への大きな変化を告げる位置にある重要な作品だという。 『海を見に行く』は、どこかの学校の時間講師らしく同時に学生である私、私の細君フク子、子の三歳のハルキチ、居候の室田が登場するが、夫婦の口論が凄まじい。読者には、いまやどちらかが家出しそうな不安を覚えさせるような按配である。妻は身ごもっていて、それでなくとも収入が少ない家庭なのに、居候までいる。居候がいつまでたっても立ち去りそうもないことに妻はますます神経過敏になり、子に八つ当たりするくらいまで興奮する。しかし、恋愛結婚であり、妻も無教養ではない。妻の口からドストエフスキーの名が出るぐらいである。言葉のやり取りが、多少滑稽でもあり、どこか情愛の熱っぽさも秘めているようにも感じられる。口喧嘩の最中、二人の恋愛結婚の夫婦生活はデリケートなものだ、と一瞬少し和解しあう場面は、流石の描写である。 「…。じゃあ私はやっぱり貴方アの愛を信じていてもいいのね…」 「ばかア…ハルキチ、飛行機だッ」 で、私たちは接吻する。 ところで、室田甚造は奇抜なゴシップがたくさん伝えられている変人である。感受性が強いものの、それから受ける印象を統一する力に欠けている。ボヘミアン気分でよく出奔する変わった癖を持つ。雑誌の挿絵を書くために、散歩の際は道すがらたくさんスケッチを書いている。何か別の作品で主人公として再登場してくるのではないかと予想、あるいは期待してしまうキャラクターであろう。 『炉辺夜話』は、短編ながら登場人物が多く、物語が恐縮された形になっているというのが第一義的な感想だった。風邪だというが吐血し寝込んでいる私三男、盛んな時代には囲い者を二三人も置いたが港築事業に失敗し落ちぶれ中風症で寝たっきりに近い父、転んだら一人で起きあがれないほど肥満した母、姉と子計吉、将来三男が面倒みる約束になっている父の姉妹であるオバサン、片腕がなくいまだ嫁ぎ先のない二番目の姉のお梅。ここでも人々の会話は辛辣である。お梅は町立病院の代診で既に子供が多い北村と恋愛関係になっていた。三男が最も信頼しているお梅に対してでさえ、会話を途中で遮って「かたわもの。行けっ」と言わしめるほどである。喧嘩は物のぶつけあいまで発展している。しかもそれは日常茶飯事のことであり、お互いにけろっと忘れてしまう。当時の一般的な家庭観では考えられないほど慇懃さに欠け喧騒な家庭であろう。三男は衆望を荷って一家の中堅にかかっていた存在だが、まだ学生でもある。友人の宇野と川田が見舞いに来た時、不意に目前で吐血してしまう。拍子木で晩飯の合図があると、子供たちは争って台所へ駆け出し二階から妓たちもドヤドヤと下りてくる。大所帯の屋敷である。三男は晩飯をサボって廊下から裏梯子を上ってお職女郎の歌吉のところへ無理に遊びに行く。歌吉は友人の川田に岡惚れなのだ。三男は誰かが自分の名を呼んでいるような気がして外に出た。外の夜は雪が降り続いている。父母に追われているような気持ちを抱きながら、途中、猛吹雪に襲われる。絵葉書屋のお葉を求めたが、そこでは川田がいて二人っきりにで何やら話し合っているの遠くから見える。三男は降雪の中歩き続けた。海に向かって歩いた。ついに、頭巾で顔を全部覆い、藁靴を脱ぎ足もマンとの中に縮めてうずくまる。 挿入的な部分の、別れた千枝子への支離滅裂な手紙、お梅が片腕を失う奇妙な夢、新聞を読むと記事の事柄に千枝子が入り混じる妄想あたりは、実験的な作風かと一瞬疑いたくなる。道徳、特に男女間の恋愛に関して当時常に最先端の価値観を追っていた石坂文学だけに、純粋に創作としての文学上でも、部分的には新しい試みを行っていたのでは、とふっと期待したくもなる。 表現的には、最後の方で、雪片を、瞬間の内に幾百千となく目を掠めて行く虫になぞらえたち、また部分的には、ビスケットの食いかけみたいな形、老人の顔に見立てているのが興味深い。それは、作品の始めの方で、北国のさびれた町には、大雪がのんのんと降りこめて、人々は目をあいていろいろな形のものを眺めているのが大儀になってくる、それゆえ眼をつぶると急に深海の底だ、と述べているだけに、意味慎重に覚えてしまった。 『キャンペル婦人訪問記』は、まとまりも主張もある優れた作品だと思う。「感情の抑揚に忠実な生活を送ること」と冒頭に作家の根本的思想が表出されている。前二作もそうだったが、ここでも登場人物、特に主人公のケーオーの文科大学の予科生の私と、妊娠した妻のフク子の会話のやりとりが、感情の抑揚によって喧嘩腰と夫婦の睦まじさが交互に現れる。フク子は女学生時代に町の教会の若い牧師と恋愛関係があった。抱擁しあったり何度もキスをしたそのような過去に、夫は嫉妬している。フク子は町の女学校を卒業し、将来女伝道師になるため横浜の宗教学校に入学した。そのとき私と知り合い、結婚した。二人は東京の大井町に新世帯を構えた。貧相な新開地で、一日でも雨が降ると地盤がとても悪くなる土地だった。しかも市内から掃溜車が来てゴミを捨てていく場所が近い。フク子は少しかっけを患っており、つわりの兆候も現れ、生活はみじめったらしい。私は、フク子は本が思っているのとは逆に捨てられたのであり、若い牧師は年増の女伝道師と結婚し琴瑟相和し賛美歌を歌いながら赤ん坊が生まれるだろうと厭味を放ったり、あるいは見せしめに曇った窓硝子に髪を振り乱した女の首縊りの絵を書いたりする。一方、フク子も策略的な置手紙を書いたりして応酬する。 ある日二人は、閑散とした電車に乗りフク子の恩師を横浜の宗教学校に訪れることになった。フク子が置き去りにした聖書その他の書物を持ち帰る目的もあった。私は散髪的メランコリーを覚える。フク子は電車の中で吐く。つわりか、乗り物酔いか定かでないが、電車の揺れに酔うのは懐かしい場面である。それでいて、悪謔を弄しあいながら二人は上機嫌でもあるのだ。私はキリスト教の狭義が紛紜することを企んでもいる。学校に着くとフク子は多くのかつての同僚たちとの久闊を叙するに忙しい。ついに校長であるキャンペル婦人に面会し、私は英語で話しかけられる。私は特にサヴナローラとメレジュコフスキーについて語る。どことなくちぐはぐな会話にも感じられるが、訪問の記念に書物をもらうことになった。外国の料理の本だが、図書館でそれが見つからず、代わって邦人述の薄っぺらな『信仰のすすめ』という無償の贈呈本だった。私は無性に腹が立った。学校から持ち帰ったのは狭い机、履き古した女下駄と大きな洗面器。書物や衣服などいいものは既に他人のものになっていたのである。二人は荷物ゆえに車掌から乗車拒否された。堤道を登り、樹立に囲まれたわずかの空地で休んだ。潅木の中から外国の可愛い子供が二人現れた。すぐその後ろから憎体な雀斑面の図体の大きい少年が姿を現し、二人に向かって「乞食! 出て行け!」と叫ぶ。さらに人を小ばかにしたように「女郎と人足め!」と放った。そしていつのまにかフク子の顔めがけて石を投げつけていたのだ。私は駆け寄り妻の肩を抱きしめると、「いや。あっちへ行って…。私はもうずっと前から貴方が嫌いになったんです。貴方は暗い、何か恐ろしい。…貴方のために私は子供を生みたくない、あっちへ、あっちへ行って…」。額の皮膚が切れ、うす赤い血が吹いていた。 『金魚』は本格的な小説である。上記の三作を読んでいるときは、上手いなあ、愚生も何か書きたいなあ、と読み進めていたが、『金魚』で俄然プロとの差を自覚させられた。我々凡人ではこの種の作品はもう書けない。夏目漱石の作品に匹敵するような、同姓の友情や三角関係、嫉妬など人間の深い心理と、いきる根底に潜む意志では操作できない世界を表出しているように思われる。後者については、原型的あるいは長い歴史を持つ社会制度からくる無意識とか、動物的あるいは本能的な意味合いの強い生理的とかではない。もっと現実的具体的な、心身にこびりついているものである。無意識は発現しないレトロ遺伝子のようなもので、確率的に稀有にしか生起しないチャンスによりその偶然性は無きに等しい。生理的なものは、常に生起しながらも意識されない反意識であり、人の行動はそれによって左右されることは極めて少なく、あっても小さい事柄に関わるだけであろう。ところが主人公の坂口には、野村の存在が居座ってしまっている。けっして野村そのものではなく、野村が放つ存在感によって縛られ自らの行動が規定されているのだ。しかもそれを受け入れ行動しているのは自ら形成した情念であり価値観であり道徳観なのだ。坂口と野村に通底する、いや他の登場人物であるミス・田口、坂口の妻ににも貫通しているものなのだ。共通世界が倫理観の微妙な強調の差異によって各々の個性の差異が顕著になり、そして個性が衝突しあう。衝突しあいながらも共通部分で妥協し合い生きていかなければならない。行き詰まったとき、そこから脱出できるものではない。目前の欲情を制御するように、共通部分における強調部分の転移を図るしかない。決して人間はそこから逃れられないのである。『金魚』はそんな世界を描いている。そこから逃れられるということは、野村によって金魚鉢から掴み上げられ、爪で腹をぷつっと潰されたように、人間にとって死を意味する。 それにしても凄い作品である。文章も無駄なく、登場人物に多少図式化が目立つ点を除けば、近代日本文学の傑作ではないかと、ただ驚くばかりだった。大衆作家石坂のみならず、日本近代文学史上、歴とした文豪なのではないか。太宰や、この野村のモデルである葛西善蔵、両者には大作が無いというのが持論だが、お二人より飛び抜けて大作家であったのではと思われてくる。太宰も、葛西も傍流にしか見えてこないから不思議だ。彼らは、家庭や地域、社会や歴史に盲目であった卑小な私小説家だけだったと。石坂は私小説からもっと広い、ルポルタージュへと極端にまで進むことなく実社会に目を向けていた。真に大人の文学である。それを初期ながら既に『金魚』という作品で披露している、恐るべき作家なのでは。とにかく文章がしっかりしていて、会話も内容のある深みを保ちながら人間味に溢れ、時に哲学的人間学的問題を彷彿とさせている。 最後の方の、坂口の夫婦喧嘩も凄まじい。昔は、愚生が少年の頃には周囲でよくあった夫婦喧嘩風景である。すごく不安になり恐い喧嘩だった。しかし、協同の農作業ではいつしか当てつけのように夫婦睦まじく仕事をし、大声で笑い合い休憩の飲食をとっていた。離婚率の高い今日、もっと冷静にことが運んでいるように感じられる。それだけ、今日の男性の精子の密度のように、愛情も希薄になっているのであろうか。 ところで、冒頭、桃割で黒襟の綺麗な、坂口の知り合いで貸し座敷の女中である"よね"が学校に使いで来るが、ここでもう"桃割"を辞書で確かめなくてはならず、また"刷毛"が読めず辞書に頼った。四字熟語を始め何度も辞書を紐解く羽目になった。 坂口は狷介孤高な野村との付き合いに大分疲れていた。長男が四歳になり、昨今まで多弁快活な暮らしに満足していたばかりなのに、「熔けた鉛が流れるような重苦しい血行を、手足の爪先まで感じ」ている。畏敬する同郷の先輩であり、異常な烈しい気魄と限度を持たぬ耽溺性を抱えている人物だった。野村は四五日同居したあと、街端れの閑静な借家に仮寓した彼のために酒を注ぎ、相撲をとり、踊り、唄い、墨をする。勤務成績は、遅刻、早退、欠勤などで満身創痍であった。妻は身篭っており、金銭的にも苦慮する。毎日一二度は会い作家・野村を理解しようと勤める骨折りと、それを執拗に阻止する妻との争いに消耗尽くし、半病人のような気息奄々の日を過ごしている。確かに野村は、朝から酒を飲んで爛酔三昧に耽っていながら、文学、料理、病気、花など、どれも完全に噛みこなされて葡萄のような滋味に富んだ小話を次々と語ることができた。さらに、ミス・田口との、危ない火遊びの領域にまで陥る関係が拍車をかけている。坂口はもともと虚弱な心身であり、ミス・田口は坂口の中に暗い惑溺を嗜好する精神があることを見抜く。坂口はまた、他人の気質を観破する才に欠け、馴染の人には無口で未知の人にはおしゃべりな傾向がある。ミス・田口との出会いのとき、それは勤務校でのことだが、田口の赤い舌まで観察する注意深さだった。が、過ぎたしゃばりには疚しさを覚える性格である。田口は美貌で若く、同僚たちから嫉視羨望を受けていた。校内での坂口と田口の噂に影響されて、坂口は逆手を取って無邪気を有邪気に変える。 坂口が野村に文学観を訴える場面は圧巻である。若輩の石坂洋次郎が既に世人の賞賛を博している葛西善蔵に対し、釈迦に説法を試みるのである。真実に対する正しい認識を欠いている。真実を水晶のように光る結晶体とみなし、その貴重で不可思議な重量を自分のものにしようと努力しているが、手に入れても個人化し、真実の去勢でしかないと主張する。 「真実は生きた流れの姿においてのみ、その強健、壮大な全面貌をわれわれに示してくれる。それを見る者は誰か。不断の節制、努力、気づかいに耐え得る者だけです」 そう言って、葛西善蔵の今は酒浸し、小さく弱い魂でしかないと批判する。かつて林檎の木の下で畑に鋤を打ちこんだ逞しい力はどこへ消えたのかと憂う。静かな閑雲野鶴の境地に安住してくださいと願う。しかし、閑寂な沈滞の境地に沈むことは受け入れない。夜通し一緒にいた妓が、皆で踊るのを誘い、坂口も蹣跚とした足取りで踊り始める。 他に、仮病で勤務を休んだ田口を坂口が見舞いに行った時の、『青い山脈』を彷彿とさせる長い会話の場面、それが原因での妻との夫婦喧嘩の場面も、心深くに刻まれる。妻が道の暗がりに倒れて死児を生んでいる幻影や、その血や苦しげな瀕死の吐息に脅かされる。陶酔した野村の、お城の公園の高台で、岩木山に対峙するエクセントリックな行動も印象的だ。「岩木山なんて結局この程度のものですかな。ハハハ…君」。そして最後の、「子と遊ぶ」…題だけ書いた原稿用紙が埃を浴びて机にのり、万年床、新聞紙の堆積、食膳、銚子、夜食の握り飯、押しても人が来ないようになった呼び鈴、臭い、その中に片肌脱ぎで胡座をかき、震える手で独酌する作家・葛西善蔵の姿が、しばらく脳裏から離れない。終いに標題が現れる、真赤な生きもの金魚。なぜ爪を鋭くして腹部にジリジリと喰い込ませなければならなかったのか。金魚は膨れ、プチリ、腹の皮が破けた。野村はすぐ、出産を済ませた産婦のように力の抜け切った姿で寝入る。それは、前後不覚の昏々とした眠り陥るべき満ち足りた疲労を示していた。 |